共働き世帯の妻が先に亡くなった場合に、30代の夫でも遺族厚生年金をもらえるようになるって本当でしょうか?【年金の常識16】
2025.09.25
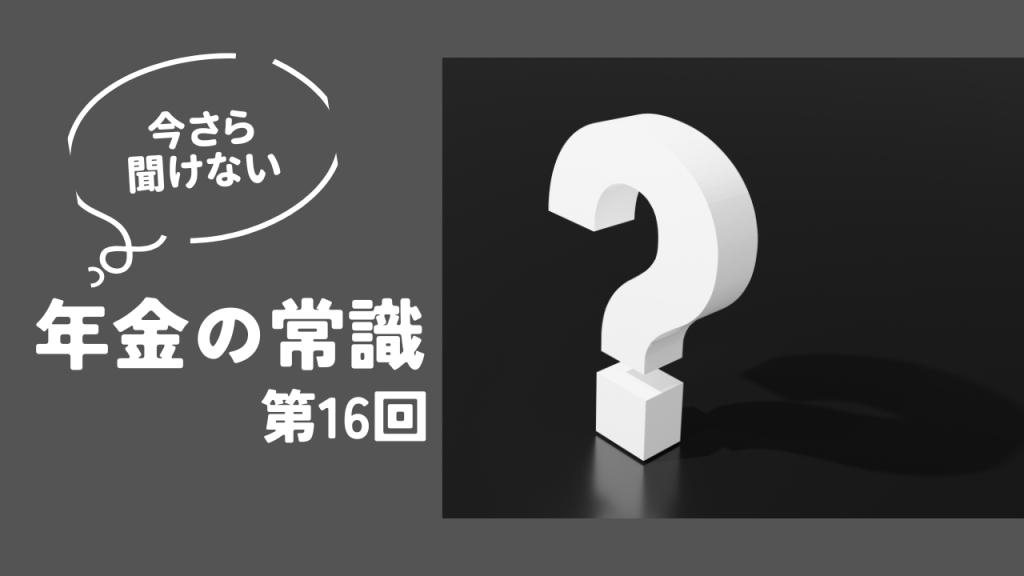
もくじ
遺族厚生年金の令和7年改正について、妻が先に亡くなった場合に、夫が遺族厚生年金をもらえるケースの拡充を社会保険労務士が解説
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
ボードゲーム系社労士&ファイナンシャルプランナーの徳本です。
年金の専門家である社会保険労務士の筆者が受けた相談や質問から、「今さら聞けない 年金の常識」として、意外と間違えやすい年金の仕組みを回答していきます。
第16回目は、妻が先に亡くなった場合に、30代の夫が遺族厚生年金をもらえるケースがあるのかという質問です。
遺族厚生年金に関しては、令和7年6月13日に改正法が成立しました。
この令和7年改正によって、夫が遺族厚生年金を受給できるケースが増えると予想されます。
この改正は令和10年(2028年)4月から施行予定とされています。
今回は、現行制度と改正施行後の違いを併せて、社会保険労務士が解説します。
なお、この記事は更新や追記などの特段の記載のない限り、投稿日現在の情報を基に執筆しています。
<スポンサードリンク>
【質問】:「30代の夫婦共働きの世帯です。法律の改正で、妻が先に亡くなった場合、夫が遺族厚生年金を受け取れるケースが増えると聞きました。30代の夫でも遺族厚生年金をもらえる場合はあるのでしょうか?」
【回答】:はい。令和7年(2025年)の改正により、令和10年(2028年)4月(施行予定)から、妻が先に亡くなった場合、一定の条件を満たせば、30代の夫でも遺族厚生年金を受け取れるようになります。
ただし、令和10年(2028年)4月(施行予定)前(=現行制度)では、55歳未満である30代の夫には原則として遺族厚生年金は支給されません。
【解説】
改正前(現行制度)は「55歳未満の夫には原則として遺族厚生年金が支給されない」という男女差がありました。
しかし改正後の令和10年4月(施行予定)以降は、男女ともに60歳未満で配偶者と死別した場合、原則として5年間の有期給付が行われる仕組みに統一されます(妻が受給者の場合には現行制度に比べて著しく不利益にならないような段階的な緩和措置が設けられています)。
具体的には:
- 子どもがいない夫婦の場合:妻が亡くなったときに夫が60歳未満であれば、原則5年間、遺族厚生年金を受け取れます。その際、「有期給付加算」により金額は従来より約1.3倍に増額されます。
- 5年経過後も受給できるケース:夫が障害状態にある場合や、収入が一定以下(単身で就労収入が月約10万円程度以下など)の場合は、5年を超えて65歳まで継続給付される仕組みがあります。
- 子どもがいる夫婦の場合:子が18歳年度末(障害がある場合は20歳未満)に達するまでは、従来(現行制度)と同様に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給され、その後に5年の有期給付+必要に応じて継続給付となります。
また、亡くなった妻の報酬が夫よりも高い場合には、新設の「死亡分割」という制度によって、亡くなった妻の厚生年金記録が分割され、夫の厚生年金記録に上乗せされる仕組みがあります。
その結果、夫が65歳以降に受け取る老齢厚生年金が、上乗せ分も合わせて計算されるため、老齢厚生年金の受給額が増額することが見込まれます(これは、「遺族」厚生年金の話ではなく、「老齢」厚生年金の話ですが、今回の改正のポイントの一つなので、併せてご紹介しておきます)。
まとめ
以上をまとめると
- 令和10年(2028年)4月から、妻が先に亡くなった場合、60歳未満の夫が遺族厚生年金を受け取れる可能性がある
- 男女差が解消され、60歳未満で死別した場合は「原則5年間の有期給付」
- 条件によっては65歳まで継続可能
- 死亡した配偶者(本件では妻)の年金記録をもとに「死亡分割」が行われ、生存している配偶者(本件では夫)の65歳以降の老齢厚生年金に増額反映の可能性がある
となります。
夫婦がともに家計を支えている共働き世帯にとっては、若くして一方配偶者が亡くなった場合には、残された配偶者が男性であれ女性であれ、家計に与える影響は少なくありません。
また、ライフスタイルの多様化によって、妻が中心となって家計を支えている世帯もあるでしょう。
今回の改正によって、これまで遺族厚生年金から取りこぼされていた「家計を支えてくれていた妻に先立たれた現役世代の夫」に遺族厚生年金支給の可能性が拡充された点は評価できるポイントだと思います。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
<スポンサードサイト>
