国民年金の保険料を払っていない期間があります。将来の年金にどんな影響があるんですか【年金の常識17】
2025.09.26
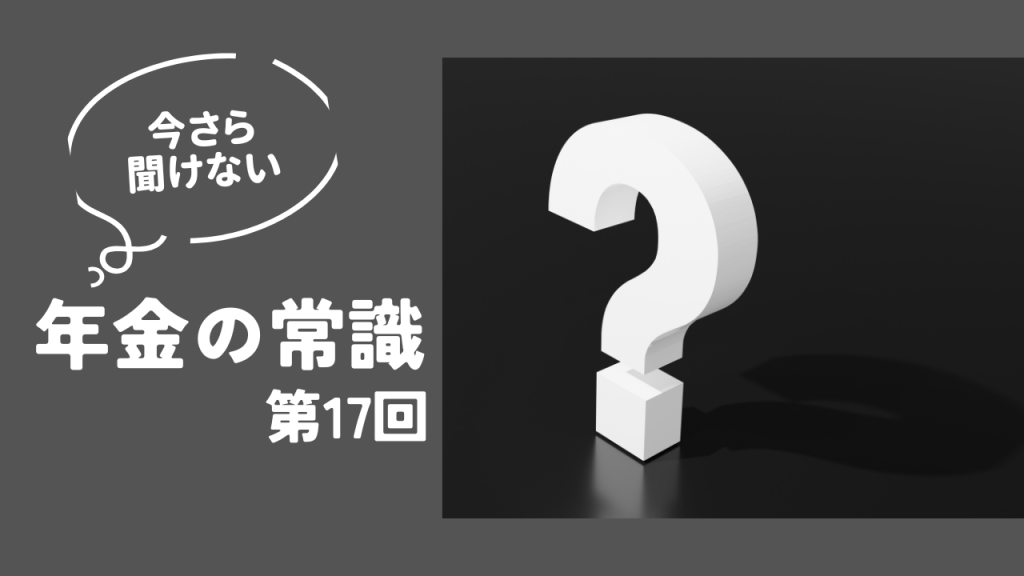
もくじ
国民年金保険料の未納期間があるとどうなる? 受給資格や将来の年金額への影響を社会保険労務士がわかりやすく解説
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
ボードゲーム系社労士&ファイナンシャルプランナーの徳本です。
年金の専門家である社会保険労務士の筆者が受けた相談や質問から、「今さら聞けない 年金の常識」として、意外と間違えやすい年金の仕組みを回答していきます。
第17回目は、国民年金保険料を払っていない期間が将来の年金に与える影響についての質問です。
「昔、国民年金を払っていなかった時期がある」「未納があると年金がもらえないの?」——こんな不安を感じている人からご相談を受けることがあります。
この記事では、年金の未納がある場合にどうなるのか、そして対処方法について、年金の専門家である社会保険労務士がわかりやすく解説します。
<スポンサードリンク>
【質問】と【回答】
【質問】:「国民年金の保険料を払っていない期間があります。将来の年金にどんな影響があるんですか?」
【回答】:国民年金の保険料を払っていない期間が、未納期間である場合は、その期間の長さによっては、そもそも老齢基礎年金がもらえなかったり、もらえたとしても年金額が減額されることになります。
また、障害年金や遺族年金の「保険料納付期間」に悪影響を与えることもあります。
<スポンサードサイト>
【解説】
国民年金の保険料を自分で納付する必要がある人とない人
国民年金では加入者(被保険者)を3種類に分けています。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。
そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者でない方を「第1号被保険者」といいます。
この第1号被保険者の方は、国民年金の保険料を自分で納付する必要があり、それを怠るとその期間は「未納期間」となります。
これに対して、第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員など)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)については、その期間は国民年金の保険料を自分で納付する必要がないので、そもそも「未納期間」の問題は発生しないのが原則です。
つまり、「未納期間」の問題が発生するのは、原則として第1号被保険者の期間ということになります。
国民年金保険料の未納があると受給の資格期間に影響する
老齢基礎年金を受け取るためには、原則10年以上の加入期間(資格期間)が必要です。
この「加入期間」には以下も含まれます。
- 保険料を払った期間
- 第2号被保険者や第3号被保険者であった期間
- 保険料の免除を受けた期間
- 学生納付特例や納付猶予を受けた期間
- いわゆる「カラ期間」(合算対象期間)
つまり、「未納期間」は加入期間にカウントされません。
これは、長期間の未納期間があると、受給資格を満たせない可能性があるということです。
その場合には、そもそも老齢基礎年金が1円ももらえなくなります。
未納は将来の年金額にどのくらい影響する?
未納期間が老齢基礎年金の年金額に与える影響について考えていきましょう。
たとえば、国民年金を満額(40年)納めた場合の老齢基礎年金の年金額は年額で約80万円(2025年度水準)です。
もし5年間の未納期間があると、その分はカウントされず、ざっくりいうと満額の約8分の1(=5年/40年)が減額されます。
例:40年中5年の未納期間=35年の納付→ 年金額:約80万円 → 約70万円に減少
このように短期間の未納でも、将来の年金額に差が出てしまいます。
年金額は一生ものですので、この約10万円の減額が65歳から85歳までの20年間続くとすれば、生涯の減額の合計は約200万円となり、未納期間分の保険料を差し引いても、さすがにこれは無視できない金額となります。
90歳、95歳と長生きすればするほど、じわじわと未納期間分の減額の影響が蓄積されていきます。
「未納」と「免除・猶予」は違う
よく誤解されますが、「未納」と「免除」「猶予」は違います。
年金額への影響を簡単にまとめると、
- 未納:手続きせずに払っていない → 将来の年金額に反映されない
- 免除:申請して承認される → 年金額には一部反映される(追納して全額反映も可能)
- 猶予:申請して承認される → 追納すれば年金額に反映される(追納が必要)
ということです。
また、免除・猶予では、年金額への反映に違いはありますが、加入期間や障害年金や遺族年金の「保険料納付要件」ではカウントされます。
また、「未納期間」の保険料は、単に納付していない状態ですので、消滅時効が成立するまでは引き続き納付義務があります。
そのため、督促や差押えの対象となり、延滞金の発生もあります。
未納期間の保険料の納付(過去2年分まで)
「未納にしてしまった!」という場合でも、納付期限から2年以内であれば保険料を納めることができます。
これは、国民年金の保険料は、納付期限から2年を過ぎると、消滅時効により納めることができなくなるからです。
未納期間分を納付することで、将来の年金額に反映されます。
ときどき「未納期間は追納で10年分遡って納付できる」と言われる方がいるのですが、これは免除や猶予の「追納制度」と混同されているのではないかと思われます。
たしかに、免除や猶予に関しては、10年以内であれば、「追納」という制度があります。
免除や猶予の場合には追納することで、将来の年金額に反映させることができます。
しかし、追納は免除や猶予の場合に限られますので、単なる「未納」の場合には納付期限の消滅時効にかかる2年以内に納付するのが原則です(なお、この消滅時効の期間に関しては、今後法改正によって延長される可能性はありますが、投稿日現在では2年です)。
未納期間は障害年金や遺族年金にも影響する
年金の種類には「老齢年金」だけでなく、「障害年金」や「遺族年金」の制度もあります。
未納期間があると、これらの給付を受けられなくなることがあります。
特に問題になるのが、「保険料納付要件」です。
保険料納付要件について概要をまとめると
- 障害年金
- 障害の原因となった病気やケガの初診日の前に「保険料納付要件」を満たしていないと、障害年金は受け取れません
- 原則として、初診日の前日において「直近1年間に未納がないこと」または「20歳以降の加入期間のうち、3分の2以上納めていること」が条件です
- 保険料納付要件は「初診日の前日」時点で判断されるため、初診日以降に未納期間分を納付した場合には、せっかく納付しても保険料納付要件にはカウントされないのが原則です
- 遺族年金
- 配偶者や子が遺族年金を受け取れるかどうかも、亡くなった方の「保険料納付要件」を満たす必要がある場合があります
- つまり、「保険料納付要件」が問題になる場合には、「未納期間」が多いと遺族が年金を受け取れなくなるケースがありえます
このようになります。
なお、免除・猶予の期間は障害年金や遺族年金の「保険料納付要件」にカウントされます。
まとめ:未納は放置せず、確認・対応を
「未納期間」の影響をまとめると次のようになります。
- 未納期間は、老齢基礎年金の受給資格や年金額に直接影響する
- 未納期間は、障害年金や遺族年金の「保険料納付要件」にカウントされず、これらの年金を受給できない場合がある
- 未納期間の保険料は過去2年分を納付することが可能だが、それ以前のものを遡って納付することはできない
- 延滞金の発生や差押えのリスクがある
このように「未納期間」を放置しておくと思わぬ悪影響を受ける可能性があります。
まずは ねんきんネットや年金定期便で自分の記録を確認 しましょう。
場合によっては、遡って免除とされることもありえますので、未納期間がある場合は、早めに年金事務所や行政機関の国民年金の窓口などに相談しておくと安心です。
また、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合(そもそも加入期間が10年に足らずに、老齢基礎年金がもらえない場合)や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合(未納期間分が減額される場合)などで年金額の増額を希望するときは、60歳以上でも国民年金に加入できる「任意加入制度」というものがあります。
任意加入を検討される場合も、任意加入の要件を満たすのかの確認などが必要ですので、まずは年金事務所や行政機関の国民年金の窓口などで相談されることをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
<スポンサードサイト>
