おひとり様の入院保証人・死後の手続きが心配? シングルライフステージの「まもり」の準備は50代から
2025.04.18
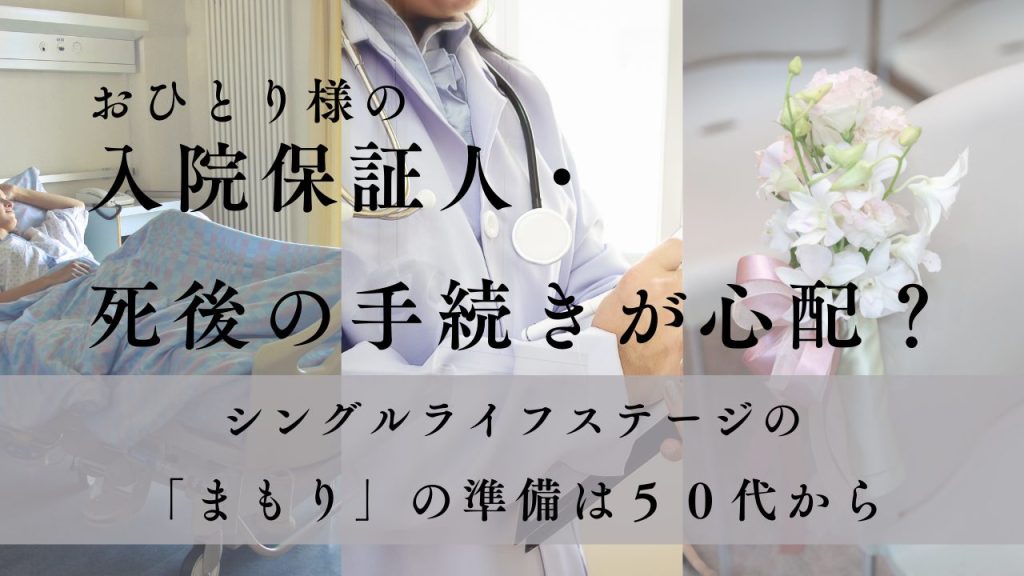
「ゆとり・つながり・まもり」の3つの「り」メイクでシングルライフステージを支援する「ボードゲーム系社労士&ファイナンシャルプランナー」の徳本です。
今回は「まもり」のお話をします。
「おひとり様」の将来について考えたとき、ちょっと気がかりなことってありませんか?
たとえば、こんな気がかり。

入院するとき、保証人ってどうしたらいいの?

自分が亡くなった後、手続きって誰がやってくれるのだろう?
50代にもなると、元気ではいても、「いざというとき」のことが気になり始めるものです。
かくいう筆者(50代)も「5080」問題の当事者であり「おひとり様」予備軍です。
14年以上成年後見業務の事務局長を務めている経験をふまえて、当事者目線で「おひとり様」のための「入院」と「死後」の備え方について、わかりやすくお話しします。
テーマは「気がかり」を「まもり」に変える——あなた自身を守る、ちょっとした準備です。
もくじ
◆ 入院時の「保証人がいない」問題
病院に入院するとき、保証人を求められることが多いのをご存じですか?
保証人とは、入院費が支払えなくなったときや、医師との連絡が必要なときに代わりに対応してくれる人のこと。
でも、おひとり様にとってこれは、意外と大きなハードルです。
最近では「本当に入院時に保証人が必要なのか」、「(どうしても保証人が見つからない場合に)保証人がいないことを理由に入院を断れるのか」という問題意識が広がっています(これは超重要なことです!)。
しかし現実的には保証人問題は根強く残っていて、未だに解決したとはいいがたいところです。
とりあえずは「決まりなので」ということで保証人を求められる可能性は高いです。
「そもそも家族がいない」「親族はいるけど遠方に住んでいる」「疎遠になっていて頼みにくい」——そんな方は、どうすればいいのでしょう?
▼ 対応策①:事前に病院とよく相談しておく
病院には患者さんの困りごとに対応してくれる相談員と呼ばれる医療・福祉の専門のスタッフが配置されていることがあります。
入院の話がでたら、相談員にあらかじめ事情をよく伝えておいて、入院時の対応策を相談しておくことが必要です。
行政など病院外の機関や組織と連携をとってくれることもありますので、入院までに時間の余裕があるなら、しっかりと相談しておきましょう。
筆者の経験上、最近は、入院保証人の問題意識が共有されており、柔軟に対応してくれる病院も増えている印象です。
きっと親身になってあなたの相談にのってくれるはずです。
なお、身寄りのない人の入院時の問題などは、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集」も参考になります。
▼ 対応策②:信頼できる人に、あらかじめ相談しておく
親しい友人や元同僚、近所の人、遠い親戚の人などに、「万が一のときに、連絡先として名前を出していい?」と前もって話しておくと安心です。
保証人までは頼めなくても、緊急連絡先としてお願いできるだけでも十分です。
入院となると、いろいろな手続きや日常の雑務を自分だけではなかなかできなくなります。
代理人のような正式な権限はなくとも、信頼できるサポート役がいてくれるだけで安心感が違います。
▼ 対応策③:民間の「身元保証サービス」を使う
NPO法人や民間業者などが「身元保証」を請け負ってくれるサービスもあります。
これは、入院や施設入所の際に必要な保証人・連絡先を専門家が代行してくれる仕組み。
中には、死後の手続きまでトータルで任せられるプランもあります。
ただし、費用は数十万円(委託内容によってはそれ以上)かかるケースもあるので、サービスの中身や料金、運営元の信頼性など、あなた自身が納得いくまでしっかりと確認して選びましょう。
正直言って、信頼性に乏しい民間業者がいないわけではありません。
最新の流れとしては、そういった問題意識を受けて、地域の社会福祉協議会や行政から委託をうけた民間業者などがこのようなサービスを行っているケースもあるようです。
今はやっていなくても、社会福祉協議会の新規の事業として始まることもあります。
いずれにしても、現時点でできることは、事前に地域の情報収集を行っておくことです。
社会福祉協議会や民間業者の最新情報を定期的に確認しておきましょう。
その際には、政府の作成した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」も参考になります(たとえば、消費者庁の「高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドラインについて」というホームページをご参照ください)。
なお、将来的には信頼できる民間業者を登録する仕組みもできてくると思います。
◆ 「亡くなったあとのこと」、準備してますか?
入院の次に気がかりなのが「死後」のこと。
お葬式、住まいの片付け、役所の届け出、銀行口座の解約……
これらの手続きは、家族がいれば誰かがやってくれますが、おひとり様の場合はそうもいきません。
「誰がやってくれるのか分からない」ままでは、周囲に迷惑がかかったり、望まない形で物事が進んでしまう可能性も。
だからこそ、あなたが生きているうちにきちんと準備しておくことが大切です。
▼ 対応策①:死後事務委任契約を結んでおく
「死後事務委任契約」とは、あなたが亡くなったあとに必要な手続きを信頼できる人(または法人)にお願いするための契約です。
葬儀、納骨、役所の手続き、住まいの片付けまで——
お願いできる内容は幅広く、公正証書にしておけば法的に契約内容を明確にしておくこともできます。
最近は、弁護士や司法書士、行政書士、NPO法人などがこのサービスを提供していることも多くなっています。
事前に死後事務に必要なお金を預けておくことになるので、「手数料と預け金の別」、「何をいくらでやってくれるのか」など契約内容をはっきり確認して、自分に合ったサービスを探しておきましょう。
なお、場合によっては、あなたの死後に法定相続人との間で問題になることもあります。
そういったトラブルを防ぐためにも、遺言作成とセットで死後事務委任契約を行うこともあります。
▼ 対応策②:遺言をつくっておく
遺言によって、あなたの財産を誰に残すかなど法律で定められた事項を生前に文書として残しておくことができます。
法的に有効な遺言書の作り方については、ここでは詳しくふれませんが、遺言の種類に自筆証書遺言というものがありますので、これは自分だけで比較的気軽に簡単に作成することができます。
もちろん、専門家に相談して公正証書遺言を作るのもいいでしょう。
ただ、遺言で一番気を付けたいのは「作ったはいいけど、どこにあるのかわからない」問題です。
特に自分だけで作った自筆証書遺言ではこういうことが起こりがちです。
遺言執行者を指定しておくといったこともできますが、そこまでいかなくても、信頼のできる人に遺言書のありかだけは伝えておくのもいいでしょう。
また、公的制度として「自筆証書遺言書保管制度」を利用することも検討してください(手続きなど詳しいことは法務局にお問合せください)。
▼ 対応策③:エンディングノートで想いを伝える
遺言に比べて、もう少し気軽に始められるのが、「エンディングノート」。
これは法的な書類ではありません。
なので、法的な効力としては遺言に劣ります。
しかし、その分自由度が高く、あなたの想いをしっかりと残すことができます。
「どんな葬儀にしたいか」「財産はどうしてほしいか」「大切な人へのメッセージ」などをあなたの言葉で残しておくノートです。
あとを託された人にとっても、とても助かる手がかりになります。
◆ あわせて考えたい「任意後見契約」
もうひとつ、老後に備えて知っておきたいのが「任意後見契約」です。
これは、あなたの判断力が低下したときに備えて、「この人に財産管理などを任せたい」と元気なうちに決めておく契約。
認知症などで判断が難しくなったときにも、信頼できる人があなたをサポートしてくれます。
死後のことだけでなく、“その前の人生”も守るための備えができる制度です。
ただし、筆者の経験からいって、任意後見制度は必ずしも広く利用されているわけではありません。
公正証書で作らなければならないこと、実際に効力を発動するには家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらわないといけないこと、任意後見人だけでなく任意後見監督人への報酬が発生してしまうことなど、使い勝手がいいかと言われれば、疑問が残る制度です。
知識として、こういった制度があるということを押さえておきましょう。
なお、任意後見と似たものに「法定後見」制度があります。
これは、ある人の判断能力が低下したと認められた際に、申立によって家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
任意後見と違って、誰を選んでほしいかをあらかじめ指定しておくことはできません。
なので、法定後見のための事前準備というのはなかなか難しいところがありますが、判断能力がしっかりしているうちに作成した遺言やエンディングノートが役に立つことがあります。
遺言やエンディングノートは、あなたが亡くなった後だけでなく、あなたの判断能力が低下した場合の準備にもなるといえるでしょう。
◆ まとめ:おひとり様でも“ちゃんと守られる時代”です
「おひとり様だからこれからが気がかり」——それは、あなただけではありません。
でも、必要な準備をしておけば、おひとり様でも安心して暮らしていける制度はあるんです。
保証人がいないときの対策、死後の手続きの準備、そして判断力が落ちたときの備え。
どれも今から始められることばかりです。
焦らなくていい。
少しずつで大丈夫。
50代の今だからこそ、あなたの人生を最後までしっかり歩み続けられるように、「まもり」の準備を始めてみませんか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
<スポンサードリンク>
<スポンサードリンク>

ボードゲーム系社労士&FP
とっくんセンセ
(徳本 博方)
ボードゲーム系社労士&FP
50代おひとりさま予備軍
「ゆとり・つながり・まもり」の3つの「り」メイクでおひとりさまのシングルライフステージをサポート
ボードゲームで楽しく「つながり」をつくり、キャリア相談・資産形成相談と年金サポートで「ゆとり」を、成年後見で最終的な「まもり」をお届けします
- 資格
- 社会保険労務士
- ファイナンシャルプランナー(2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFP)
- 宅建士
- 経歴
- 一般社団法人萩長門成年後見センター事務局長(現)
- 弁護士事務所パラリーガル(勤務17年以上)
- 山口県萩市出身
- 萩高校、慶応義塾大学文学部