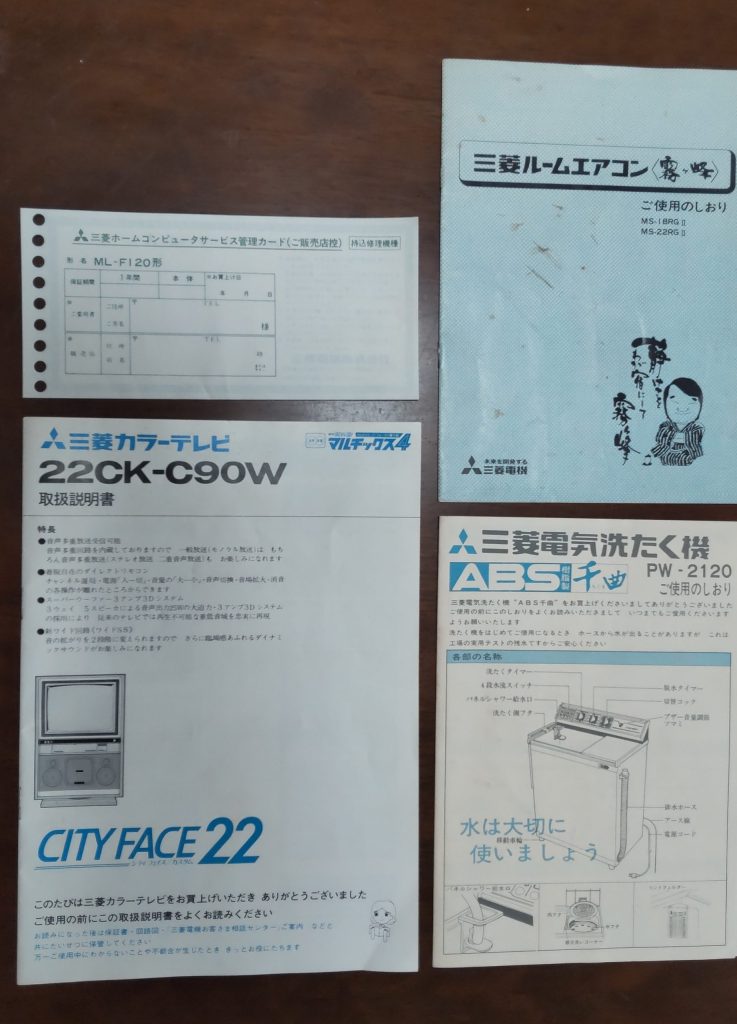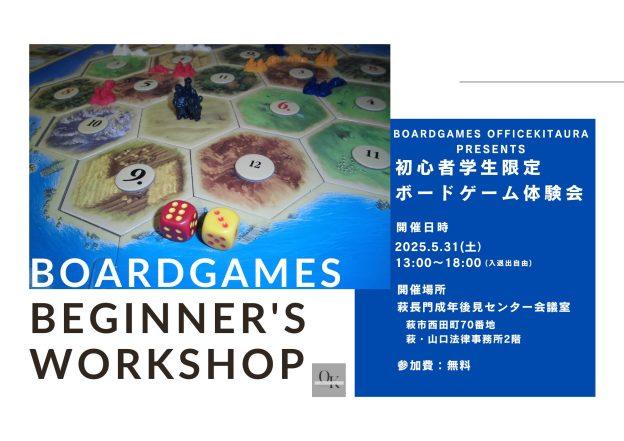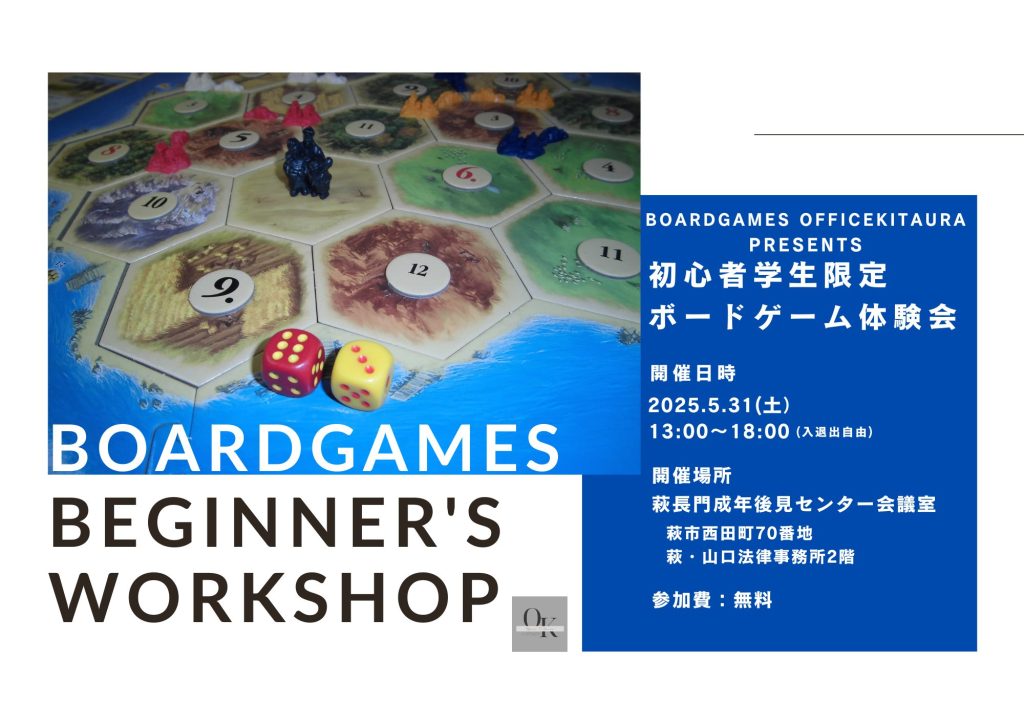「そろそろ親の介護が始まるかも……どうしたらいいのだろう」
「親の介護費用、できるだけ抑えたいけど……いい方法はないかしら」
50代になると、そろそろ親の介護のことが気になってきます。
そう思っても、具体的な対策がわからず、不安を抱えたままの方は多いのではないでしょうか。
かくいう筆者自身も「5080」問題の当事者です。
今回は、社労士&ファイナンシャルプランナーとして、14年以上成年後見制度の社会保険最適化業務に取り組んでいる筆者が、成年後見業務を通じて学んだ介護費用を抑制する方法をお届けします。
結論から言います。
それはずばり「住民税非課税世帯」になることです。
「住民税非課税世帯」であれば、介護サービスの自己負担を軽くできる制度があるのです。
この制度を知っているか知らないかだけで年間で数十万円以上の差が出ることもあります。
今回は、そんな「介護×住民税非課税世帯」のメリットをわかりやすく解説します。
なお、こちらの情報は投稿日現在のものですのでご注意ください。
<スポンサードリンク>
「住民税非課税世帯」とは?
住民税には「所得割」と「均等割」の2種類があり、世帯全員がそのどちらも課税されない場合にその世帯は「住民税非課税世帯」となります。
たとえばこんなケースが該当します(東京都23区内の場合)
- 所得割・均等割とも非課税
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
- 〈東京23区内の場合〉
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円 以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円 以下
※東京都主税局ホームページから引用
東京都23区の例でいうと、たとえば65歳以上の単身世帯で収入が公的年金だけの場合には、年金収入が年間155万円以下の場合に住民税非課税世帯になります。(公的年金収入155万円から公的年金等控除額110万円を引いたら45万円になりますね。これを「155万円の壁」というひともいます)。
ただし、住民税が非課税になる基準は住所地(その年の1月1日のもの)によって変わることがあります。
これを級地区分といいます(ちなみに、筆者の住んでいる山口県萩市の単身世帯の住民税非課税の基準は38万円以下ですので、先ほどの「155万円の壁」は「148万円の壁」と読み替えることになります)。
住民税非課税の基準については、お住まいの自治体でご確認することが必要です。
今回の記事では、各制度自体をしっかり知っていただくために、「誰の扶養にもなっていない単身世帯の親(65歳以上)」という設定で考えていきます。
実際には、同一世帯に課税対象者がいたり、誰かの扶養になっていたりということもあるでしょう。
そういった場合には世帯分離をした方がいいのか、扶養から外れた方がいいのかなど、状況に応じてどちらがより大きなメリットがあるかを検討する必要がでてきます。
住民税非課税世帯が介護で得られる3つのメリット
住民税非課税世帯の方が介護の現場で使うことができる3つの制度をご紹介します。
ここでは、
- 高額介護(介護予防)サービス費
- 特定入所者介護サービス費(補足給付)
- 社会福祉法人の「利用者負担軽減制度」
の3つを紹介します。
高額介護(介護予防)サービス費の自己負担上限が下がる!
在宅介護や通所介護などで発生する介護保険サービス費用(利用料)には、要介護度等による利用限度額が定められており、さらに所得区分によって月ごとの自己負担額に上限が設けられています。
そして、支払った自己負担額がその上限を超えている場合には、差額に相当する金額が申請によって支給されることになります。
これを「高額介護(介護予防)サービス費」といいます。
対象者にはお住まいの自治体から申請書などが送られてくると思いますので、申請手続きを必ず行いましょう(申請主義なので、放っておくと時効で消滅する可能性がありますので要注意です)。
投稿日現在の住民税非課税世帯の高額介護(介護予防)サービス費利用者負担上限額は月額2万4600円(年間収入が80万円以下であれば1万5000円)です。
たとえば、要介護度3のひとの1ヶ月の居宅サービス費が27万円(利用限度額は27万0480円)だった場合、自己負担額(1割負担)は2万7000円となり、限度額2万4600円を超えた2400円が支給されます。
仮にこの支給が同じ条件で5年間続いた場合には、2400円×12ヶ月×5年=14万4000円となります。
介護は長期間に及ぶケースも多いので、毎月の支給額はそれほど多くはなくても、それが積もり積もれば無視できない金額になるということです。
入所施設の食費・居住費が軽減される特定入所者介護サービス費(「負担限度額認定」)
特養などの入所施設では、介護費用のほかに「食費・居住費」が発生しますが、住民税非課税世帯で預貯金額の資産要件など諸条件を満たせば、「特定入所者介護サービス費(補足給付)」により費用が軽減されることがあります。
具体的には、自治体から「負担限度額認定」を受けることで、毎月の施設での食費・居住費が軽減された額で請求されます(先ほど紹介した高額介護(介護予防)サービス費はいったん払った後での差額分支給でしたが、こちらはそもそもの請求金額が安くなるので、より経済的負担が減ります)。
こちらも申請が必要ですので、対象者は自治体にご相談のうえ、負担限度額認定の申請を行ってください。
たとえば、筆者の住んでいる山口県萩市では、住民税非課税世帯のひとの年収(非課税年金も含む)が80万円超120万円以下のひとは「第三段階①」に該当するとされ、特養等の住居費は多床室で日額430円、食費は日額650円とされています(投稿日現在)。
つまり住居費と食費の合計は日額1080円となります。
30日の月であれば、1080円×30日=月額3万2400円という計算です。
もしこれが住民税非課税世帯「第三段階①」ではなく標準費用額(めやす)であれば、特養住居費(多床室)日額915円、食費日額1445円で、合計日額は2360円となり、30日なら2360円×30日=7万0800円となります。
その差額は、7万0800円-3万2400円=3万8400円です。
これが1年間なら46万0800円、5年間なら……
これほどの差がつくのは驚きです。
住民税非課税世帯の方が特養などに入所される場合には、預貯金額などの条件はありますが、介護保険の限度額適用認定は必ず検討しましょう。
社会福祉法人の「利用者負担軽減制度」が使えることも
次にご紹介するのは、社会福祉法人の「利用者負担軽減制度」です。
収入や預貯金額が基準以下などの要件を満たせば、社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者負担が軽減される制度です。
正直言って、筆者は今の仕事をするまでこの制度を知りませんでした。
なぜならば、この制度は社会保険の制度ではないからです。
筆者は社会保険労務士で、公的年金や公的医療保険の専門家です。
また、ケアマネさんほどではありませんが、広義の社会保険として介護保険の知識もある程度は持っています。
しかし、この制度は福祉の制度ですので、社会保険労務士の専門範囲外なのです。
福祉の専門家以外でこの制度知ってる人はどの程度いるのでしょうね……
この制度は、介護保険の制度と併せて使うことができます。
もし該当するのであれば躊躇なく使っていきましょう(預貯金額などの条件はシビアですが)。
利用には申請が必要なので、まずは事業所や自治体に相談しましょう。
「障害者控除対象認定」制度を知っていますか?
さきほど、65歳以上の単身世帯で公的年金収入のみの場合、住民税非課税世帯になるためには「155万円の壁」が存在するというお話をしました(なお、公的年金が障害年金や遺族年金などの非課税年金の場合には、そもそも非課税なので155万円の壁はありません)。
では、老齢年金などの年収が155万円の壁を超えてしまう場合には、住民税非課税世帯にはなれないのでしょうか。
ここで検討したいのが「障害者控除対象認定」です。
住民税非課税世帯の要件を思い出してください。
「障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下」というのがありましたよね。
税法上の「障害者」であれば、所得が135万円以下であれば住民税非課税世帯となるという規定です。
つまり、障害者等であれば、公的年金等控除額(110万円 ※65歳以上で年金年収330万円未満の場合)を加算すれば、「155万円の壁」は「245万円の壁」まで上がるということです(壁が上がった方が住民税非課税世帯になりやすいです)。
このような税法上の障害者と認められるには、いわゆる「障害者手帳」を有しているケースが考えられます。
しかし、「障害者手帳」を持っていない場合であっても、要介護認定を受けた高齢者は、自治体の判断により「障害者控除」の対象になることがあります。
これを「障害者控除対象認定」といいます。
自治体から「障害者控除対象認定」を受ければ、住民税非課税世帯になる可能性がでてくるのです。
たとえば、公的老齢年金のみで年収180万円(月15万円)の場合、このままだと住民税非課税世帯にはなれませんが、障害者控除対象認定を受けて手続きを行った場合には住民税非課税世帯になることが可能となります。
障害者控除対象認定の基準や方法はお住まいの自治体に相談してください。
なお、障害者控除対象認定を受けたあとは、自治体の税務課に障害者であることを伝える必要がありますので、確定申告や住民税申告などの手続きもお忘れなく。
おわりに
介護費用は、ただでさえ精神的・身体的な負担が重なる中での出費になります。
しかし、制度を知り、上手に活用することで、負担を軽くすることは十分に可能です。
ただし、こういった制度のほとんどは「申請主義」を採用しています。
平たく言えば「言ってくれればやるけど、そっちが言うまでは知りませんからね」ということです。
まさに「知ってるひとだけが得する」制度と言っても過言ではありません。
なかには自治体から「あなたは対象者ですので申請ができます」といった趣旨の文書が送られてくることがあります。
また、一度申請しておけば、その後はいちいち申請しなくても自動的に対応してくれる場合もあります(これはありがたい!)
しかし、高齢者の場合、そういった文書はよく読まずに、そのまましまい込んでいるケースが散見されます。
実際に、筆者が成年後見業務でかかわったひとの中には自治体からのお知らせ文書を放置していたケースが複数ありました。
成年後見人が就任後ただちに手続きを行ったものの、一部は時効で消滅してしまっていたケースもあります。
これが申請主義というものかと実感しました。
いずれにしても、これらの制度を知っているだけで、介護に向き合う“心の余裕”と“家計の安心”が多少なりとも生まれると思います。
親の介護が心配になった今こそ、一度ご家庭の収入状況や制度適用の可能性をチェックしてみてください。
この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

ボードゲーム系社労士&FP
とっくんセンセ
(徳本 博方)
ボードゲーム系社労士&FP
50代おひとりさま予備軍
「ゆとり・つながり・まもり」の3つの「り」メイクでおひとりさまのシングルライフステージをサポート
ボードゲームで楽しく「つながり」をつくり、キャリア相談・資産形成相談と年金サポートで「ゆとり」を、成年後見で最終的な「まもり」をお届けします