できないことの方が多い保佐人業務

オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
社会保険労務士の徳本です。
筆者は、法定成年後見業務を専門に行う法人の事務局長を務めています。
成年後見業務(保佐業務)をやっていて困ることの一つに、「保佐人の代理権が設定されていないのに、その業務を保佐人が行うことが当然とされている」というケースがあります。
今回は、このような保佐人の権限外の行為について現状とその問題点(できれば解決策まで)を考えてみたいと思います。
<スポンサーリンク>
保佐人のできることは限られている
保佐人のできること(権限)は、原則として、民法13条1項各号に定められた事項(たとえば、借入や保証契約(2号)、不動産の取引(3号)など)についての同意権と、それらを本人が保佐人の同意なしに行った場合の取消権(ないし追認権)です。
たとえば、本人が借金をしようとした場合には、保佐人の同意を得て契約しなければならず、仮にその同意なしに契約をした場合には保佐人がその契約を取り消すことができるということです。
また、これらの同意権の範囲は、拡張することもできます(民法13条2項)。
ただし、契約を行うのはあくまでも本人であり、保佐人はそれに同意をすることができるというだけです。
この点、「成年後見人」の場合には、本人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為については本人を代表する(=法定代理人として法律行為ができる)とされていること(民法859条1項)と比べると、大きな違いがあります。
もちろん、保佐人の場合にも、代理権付与の審判(民法876条の4)を得ることで、一定の行為については代理権が行使できますが、成年後見人のように、広範な代理権を一般的に行使することはできないのです。
このように保佐人の権限が限られていることは、本人(成年被後見人と被保佐人)の現有能力の違いに由来するものですし、そもそも広範な代理権行使は本人の人権の制約にもつながるので、理にかなった制度ではあります。
しかし、実際の保佐人の活動の現場では、困ったことも生じるのです。
権限外行為を求められる現実
実際に保佐人として活動をしていると、民法13条の同意権(またはその取消権)を行使する場面というのはそれほど多くはありません。
よく考えずに不相当な契約をしてしまったとか、不動産を売却しなければならないとか、日常生活においてはそうそう頻繁にあることではないのです。
むしろ、保佐人が行うことの多くは、医療費等日常の支払いや金融機関の取引(預貯金の管理)といったことであり、これらの行為に関しては予め保佐人に代理権が付与されていることがほとんどです(もしくは、選任後必要に応じて新たに代理権を付与してもらうこともあります)。
このような類型的な行為については、代理権付与で対応できるのですが、イレギュラーなことが生じて、保佐人がその対応に追われることも少なくありません。
たとえば、年金や医療保険といった社会保険の申請や福祉関係の行政手続き、ときには収入がないことの税務上の手続などがあります。
保佐の場合、本人が行為を行うのが原則なので、「本人にやらせればいい」と言われればそのとおりなのですが、本人だけではできないからこそ保佐人に対応が求められるのであり、それこそが、本人や関係者(果ては黙示に裁判所までも)が保佐人に求めているものなのです。
そのため、保佐人への代理権付与の項目が多岐にわたってしまい、何のために保佐人の権限を制限したのかよくわからなくなるといった現象も起きます(それでも、それらの代理権の範囲を超えた問題が生じることも少なくないのですが)。
それならば、「その都度、裁判所に代理権付与を求めればよい」とか「個別に本人と委任契約を結んで代理権を取得すればよい」というご指摘もあるのでしょう。
たしかにお説ごもっともです。
時間も手間も費用も考えずにすむのならそのようにしますが、実際にはそれができない現実もあります。
また、本人から保佐人が個別に代理権を取得する場合、保佐人が本人との委任契約の一方当事者になることの適否の問題もあります。
さらに言えば、そもそも業際問題(法律で許された者以外への代理ができない場合)が絡んでくることもあります。
「それができるのなら、とっくにしてるよ」というのが本音なのではないでしょうか。
結局のところ、このような場合、現場では、保佐人が本人のところに行って事情を確認し、本人が書類を作成できるように援助し、場合によっては提出を代行するといったように、「本人が行為を行った体裁」をつくって、臨機応変に対応せざるをえないのです。
保佐人は日常業務の負担が大きい
そもそも、保佐人の日常業務に関しては、成年後見人のそれよりも相対的に手のかかることが多いものです。
たとえば、重度の障害によって入院・入所している成年被後見人と、軽度の障害で自宅で暮らしている被保佐人とでは、後者の方が日常業務の負担が大きいというのは、実際に後見業務に携わった方なら実感できるのではないでしょうか。
前者の場合、前述のように成年後見人には広範な権限があり、成年後見人は代理権を使って様々な手続きを行えますし(その是非はひとまず置いておいて)、そもそも入院や入所中であれば、病院や施設のおかげで、日常の生活トラブルなどは抑えられます。
それに対して、後者の場合には、保佐人の権限が限定的であるにもかかわらず、本人だけでは対応できないことが生じれば、そのフォロー(権限外であっても)は必要ですし、在宅であれば、日常の様々な困りごとが日々生じてきます。
そして、そのような日常の場面でこそ、保佐人の権限外行為が求められるのです。
保佐人が評価されない現実
しかしながら、こうして保佐人が権限外の行為を行ったとしても、保佐人の評価にはつながらないのが原則です。
たとえば、保佐人の同意権(場合によっては代理権)によって不動産を処分して利益を得たとか、保佐人が取消権を行使して財産を取り戻したとかいう場合には、金銭的に効果が見えるのでその評価もある程度客観的に行えるでしょう。
それに対して、たとえば、本人だけではできない社会保険や福祉の手続きを保佐人が手伝ったからといって、これを客観的に評価するのはなかなか難しいのではないでしょうか(身上監護の一環としてどの程度評価されるのかは正直よくわかりません)。
しかも、権限外の行為、すなわち業務外の行為であれば、そもそも評価の対象外とされても文句は言えません。
保佐人業務の評価が必ずしも正当に行われていないのではないかという現実があるのです。
それでも保佐人制度はもっと活用されるべき
以上のように、①保佐人の権限が限定されていること、②権限外の行為を(当然のように)期待されていること、③保佐人の権限外行為が求められる場面が少なくないこと、さらに④保佐人の業務の評価が難しいことという理由から、保佐人の業務は負担が大きいといえます。
さらに言えば、(成年被後見人に比べて)被保佐人の現有能力が高いので、方針や意見の違いから、本人と保佐人との間に衝突が起きやすいという傾向もあります。
こういった理由から、専門職の方からも「保佐人はこりごり」とか「保佐人は割に合わない」といった愚痴を聞くこともなくはありません。
しかし、保佐人制度は、成年後見人制度よりも本人の権限の制限が緩やかであり、本人としっかりコミュニケーションをとることで、意思決定支援を行いやすいというメリットもあります。
そういう意味において、保佐人制度はもっと積極的に活用されるべき制度だと考えています。
積極的に専門家に依頼できる仕組みづくりを
では、前述の①~④の問題のように、保佐人が「権限なき責任を日常的に無償で負わされている」という現状をどうすればよいのでしょうか。
その対策の一つは「専門家への依頼」だと思っています。
社会保険手続は社労士に、行政手続は行政書士に、税務申告は税理士にといったように、各専門家への依頼がスムーズにできれば、保佐人が権限外の業務を負担することは少なくなるでしょう(専門家に依頼すれば業際問題も生じません)。
ただ、実際のところ、専門家への依頼に、それほどお金がかけられないという問題があります。
また、「わざわざ専門家に依頼するような内容ではないのではないか」ということで、依頼を躊躇することもあるかもしれません(専門家側でも、小さな手続を敬遠するということがないわけではないでしょう)。
そのようなことのないように、ちょっとしたことでも、できるだけ安価で気軽に効率的に、保佐人が各専門家に依頼できるような仕組み作りが必要なのではないかと思っています。
この点、弁護士の法テラスのような制度や公的な援助の制度があればいいのにと思うところですが、現実的にはさすがに難しいでしょう。
個人的には、現在進行中の成年後見の「中核機関」構想の中で何らかの仕組みをつくってもらえないものかと期待をよせているところです。
保佐人制度をもっと活用するためにも、保佐人の業務負担の軽減はとても大切なことなのですから。
現場では、「成年後見相当」とされる人の中でも、その能力には幅があり、限りなく「保佐相当」に近いのではないかと思われる人もいます。
本来、本人の能力が回復しているのであれば、成年後見から保佐に変更する手続きをするべきなのですが、仮に、保佐に変更になることによって生じる業務負担増が原因で、それを躊躇うことがあったとすれば、本人の人権侵害に直結する大きな問題だと思っています。
実際にそのようなことはないことを願いますが、現実問題として、成年後見と保佐との利用率の差をみると、考えてしまうものがあります。
保佐人制度が有効に機能するように、必要な仕組みを真剣に構築すべき時期だと思っています。
せっかくの「中核機関」構想ですので、これを機に是非改善していただきたいものです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
<スポンサーリンク>
あわせて読んでいただきたい関連記事
こんなはずでは・・・と後悔する前に、知っておきたい成年後見制度の注意点
前後の記事
前の記事:第50回社会保険労務士試験の試験問題の公開を受けて思ったこと(選択式感想)
後の記事:「第10回 対話型勉強会」のお知らせ

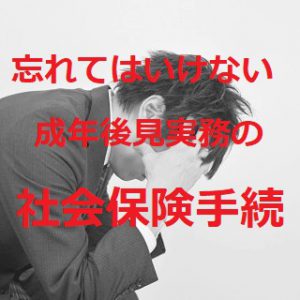
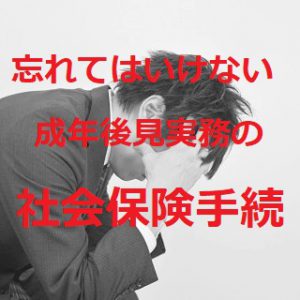 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。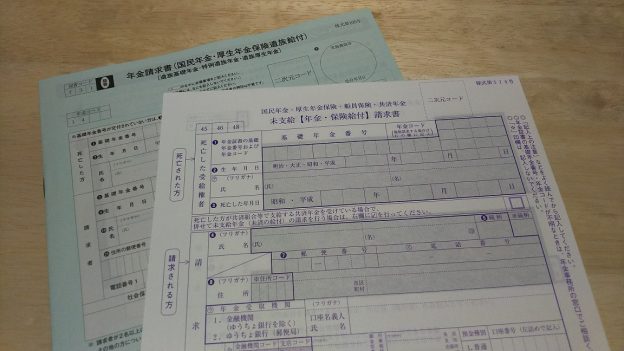
 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。 平成29年3月、最高裁判所事務総局家庭局から「
平成29年3月、最高裁判所事務総局家庭局から「