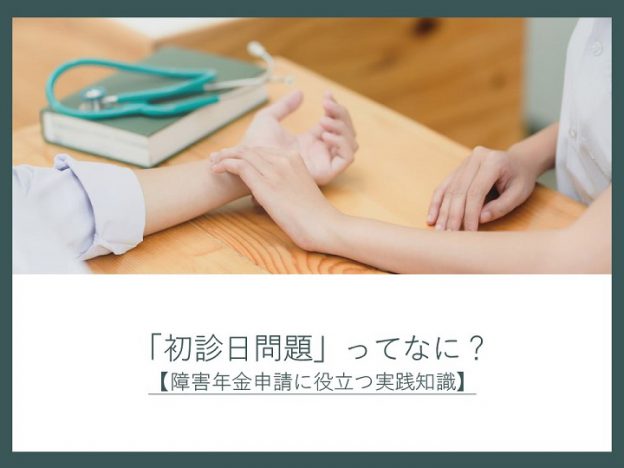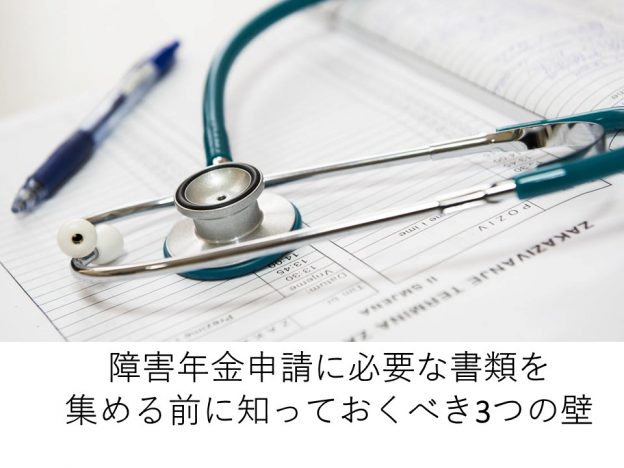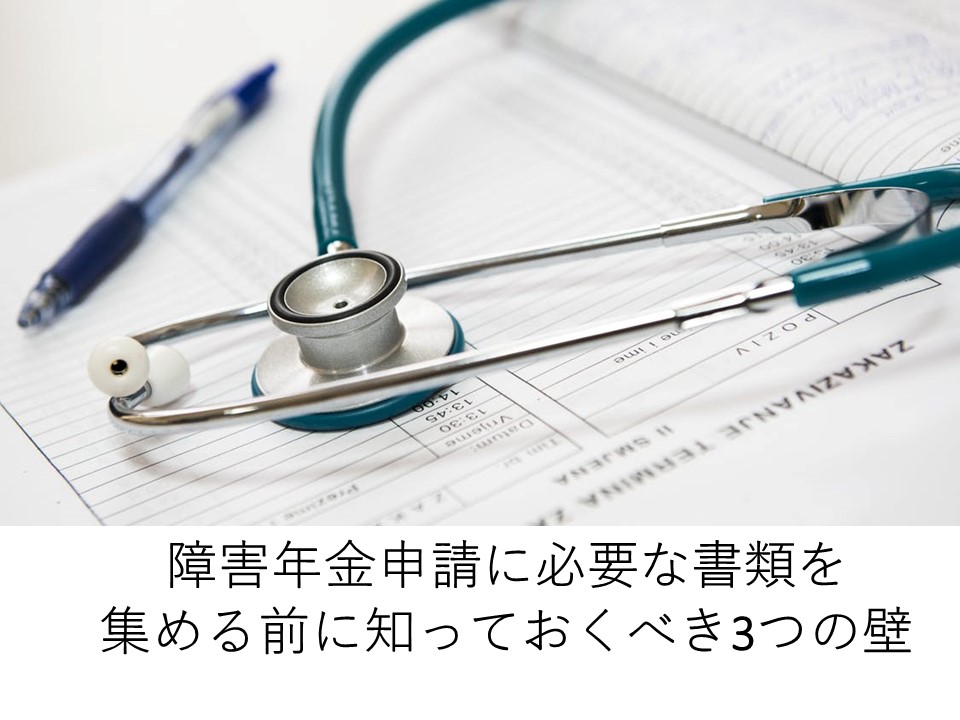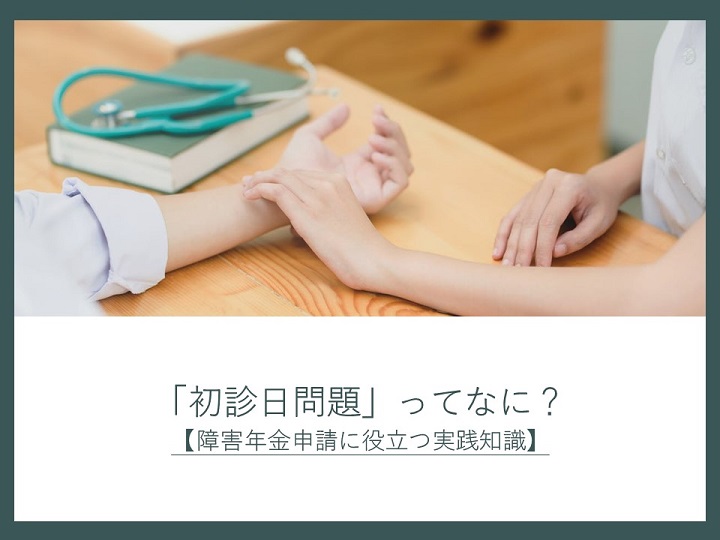
社会保険労務士・オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
障害年金の専門家(報酬をもらって障害年金申請を代理することのできる国家資格)である社会保険労務士が、「障害年金申請は自分でできる」をテーマに、障害年金申請に役立つ実践知識をお伝えしていくシリーズです。
今回のテーマは「初診日」。
初診日に関係して、筆者がよく聞くご質問やご相談としては、
- 障害年金申請の初診日って簡単にわかるはずだと思うけど、何が問題なのかよくわからない
- 障害年金申請の初診日で問題になるのはどういうケース?
- 障害年金申請の初診日の問題に対処法はあるの?
といったものがあります。
そこで、この記事では、
- 障害年金申請の「初診日問題」ってなに?
- 障害年金申請の初診日問題が起きる具体的ケース
- 障害年金申請の初診日問題の対処法
といった項目順にお伝えしていきます。
なお、障害年金については「請求」と表記する方が正確です。
しかし、「申請」という表記が一般的に使われていることもありますので、この記事ではわかりやすさを優先して、「申請」と表記することにします。
この記事の情報は、特別の記載のないかぎり、投稿日現在のものです。
<スポンサードリンク>
障害年金申請の「初診日問題」ってなに?
障害年金申請の情報をネットなどで調べていると、やたらと「初診日」という言葉を聞くと思います。
少し調べれば「初診日とは障害の原因となった傷病につき初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」という情報がすぐにでてくるでしょう。
それはそのとおりなのですが、ここでは実践的な知識として、初診日についてもう少し掘り下げてみようと思います。
それを「初診日問題」ということにしましょう。
ここでは、①初診日問題とは何なのか、②そもそも初診日にどうしてそこまでこだわるのか、③どうして初診日問題が起きてしまうのかについてみてきましょう。
初診日問題ってなに?
ここでの「初診日問題」とは、初診日が特定できずに障害年金申請に支障をきたす状態のことをいいます。
「初診日なんて初めて病院に行った日でしょ? それがわからないひとなんているの??」って思ったひとはいませんか?
たしかに、ふつうに考えれば、初診日の特定で苦労することはないように思えます。
ひとつの医療機関に通っていて通院期間も短い場合には、初診日問題が生じることはほとんどありません。
しかし、複数の病院に通っていたり、長期間にわたって通院をしているような場合にはどうでしょうか。
初診日問題が発生する可能性が高くなります。
そのため、この初診日問題が壁になって、障害年金申請をあきらめてしまうひとも現実にいるのです。
初診日問題の困ったところは、初診日が特定できなければ障害年金はもらえないということです。
これに対して、「もし初診日が特定できなくても、現時点で障害の状態にあることが医学的に証明できるなら、障害年金をもらえるんじゃないの?」と思ったひともいるかもしれません。
しかし残念ながら、現実はそうなっていません。
いくら現時点での障害の状態を医学的に証明しても、それだけでは障害年金はもらえないのです。
それほど障害年金申請において初診日は重要な要素だということです。
ではつぎに、どうして障害年金はそこまで初診日にこだわるのかを考えてみましょう。
初診日の特定はなぜ必要か?
障害年金が初診日にこだわる理由は大きく3つあります。
それは、
- 初診日に加入していた年金を基準にしてどのような障害年金がもらえるかが決まる(加入要件。そもそも障害年金がもらえるのかどうかや障害厚生年金までもらえるのかどうかに影響)
- 初診日の前日を基準にして保険料をちゃんと納めていたかどうかが決まる(納付要件。そもそも障害年金がもらえるのかどうかに影響)
- 初診日を基準にして障害認定日が決まることがある(いつから障害年金がもらえるのかや認定日請求か事後重症請求かという申請の方法にも影響)
という理由です。
つまり、初診日が特定できないと、そもそも障害年金がもらえるのか、もらえるとして障害厚生年金までもらえるのか、いつから障害年金がもらえるのかが決まらないということなのです。
しかし、初診日=初めて病院で診療を受けた日の証明がどうしてそんなに難しいのでしょうか。
初診日問題がなぜ起きるのかを考えてみましょう。
初診日問題はなぜ起きる?
初診日問題は、初診日当時の医療記録が現時点で確認できないことが原因で起きます。
医療記録の保存期間が経過するなどの理由で、初診日の医療記録が確認できないということです。
そして、それが起きるのはだいたい次のようなケースです。
- 終診(転医・中止)
- 別の傷病が原因で現在の疾病が生じている
- 現在の疾病が別の疾病と同一疾病として扱われてしまう
それぞれの具体的なケースをみていきましょう。
障害年金申請の初診日問題が起きる具体的ケース
終診(転医・中止)
初診日当時の医療機関での診療が終わって時間が経過しているために、医療記録が破棄されているようなケースです。
別の病院に変わった場合や治療を中止したような場合です。
医療機関そのものが廃院となっているような場合もあります。
物理的に記録がなければ、医療機関も初診日を証明することができないのです。
別の傷病が原因で現在の疾病が生じている
現在の疾病で初めて病院で診療を受けた日が初診日だと思っていたら、その疾病の原因となった傷病が確認されて初診日がさかのぼってしまうケースがあります。
これを「相当因果関係」の問題といったりもします。
たとえば、腎不全によって人工透析を受けることになって障害年金を申請しようとしたところ、その原因が糖尿病だと認められたために、糖尿病によって初めて病院で診療を受けた日が初診日となるようなケースがこれにあたります。
糖尿病は治療に長期間を要することもあるため、相当因果関係が認められることによって初診日が10年以上さかのぼってしまうということも起こりえます。
糖尿病の他にも、肝炎と肝硬変、事故や脳血管疾患によって精神障害を発症したような場合などに相当因果関係があるとされています。
もっとも、初診日の長期間のさかのぼりの問題は糖尿病ほどではありませんが。
いずれにしても相当因果関係によって初診日がさかのぼったために、医療記録が確認できない状態が起こりえるのです。
現在の疾病が別の疾病と同一疾病として扱われてしまう
精神疾患の場合に起こりやすいのですが、現在の疾病が別の疾病と同一疾病として扱われるケースがあります。
たとえば、過去にA病院で不眠を訴えて治療を受けていた場合で、その後何年か経ってB病院で統合失調症の診断を受けた場合に、A病院での初めての診療日が初診日とされるようなケースです(神経性不眠症と統合失調症が必ず同一疾病になるというわけではありません。具体的な事情のもとで同一疾病として認定される場合があるということです)。
この他にも発達障害とうつ病、知的障害とうつ病なども同一疾病として扱われることがあります。
このような場合も、初診日が先発した別の疾病の診療日までさかのぼることになります。
なお、先発の疾病が知的障害である場合には、知的障害の初診日は出生日とされていますので、初診日の特定の問題は生じません(ただし、障害厚生年金がもらえないという別問題が発生します)。
障害年金申請の初診日問題の対処法
受診状況等証明書が添付できない申立書
転院などによって現在の医療機関で初診日の証明ができない場合には、初診日に受診した医療機関が作成した「受診状況等証明書」を提出するのが原則です。
しかし、初診日問題が生じる場合には「受診状況等証明書」が提出できないことがほとんどです。
そういった場合には「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することになります。
そして、いくつかの医療機関の受診歴がある場合には、古い順に「受診状況等証明書」がとれるまで繰り返していきます。
しかし、受診状況等証明書が添付できない申立書それだけで初診日が認められることはまずありません。
それを補うための書類や資料が必要になります。
たとえば、
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 上記手帳等申請時の診断書
- 生命保険、労災保険等の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録 ・・・など
の客観的な裏付け資料によって初診日を特定する必要があります。
では、こういった初診日を特定できる客観的な裏付け資料がない場合にはどうしたらいいのでしょうか。
この点については「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」という通知があります。
その概要を確認していきましょう。
障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い
初診日を明らかにすることができる書類を提出できない場合の取り扱いを簡単にまとめると、以下のようになります。
- 20歳前に初診日がある場合、2番目以降の医療機関の受診状況等証明書から、障害認定日が20歳前であることが確認できる場合で、かつその受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合
- 2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書に、医療機関が作成した資料(診療録等)を基にした請求者申立の初診日が記載されている場合
- 請求の5年以上前に記載された資料を基にしたもの ⇒ 請求者の申立日を初診日とできる
- 請求の5年以上前に記載された資料を基にしたものではないが、相当程度前であるもの ⇒ 参考資料(領収証など)と合わせて請求者の申立日を初診日とできる
- 「初診日に関する第三者からの申立書」(第三者証明)を添付する場合
- 「第三者」とは三親等以内の親族以外の者をいう
- 初診日が20歳前のとき(厚生年金加入期間を除く) ⇒ 第三者証明(原則複数必要)だけでよい
- 初診日が20歳以降(20歳前の厚生年金加入期間の場合含む) ⇒ 第三者証明(原則複数必要)+その他の参考資料が必要
- 第三者が担当医師等医療従事者であればそれのみの証明でよい(その他の参考資料は不要。複数不要)
- 一定期間(始期と終期を参考資料等で特定する必要がある)内に初診日があって、そのどの時点でも納付要件を満たす場合
- その期間中同一の公的年金に加入 ⇒ 請求者の申立日を初診日とできる
- その期間中異なる公的年金に加入(20歳前や60歳以上65歳未満の待期期間の混在を含む) ⇒ 障害基礎年金は認められるが、障害厚生年金は参考資料が必要
ここでは概要を紹介するにとどめますが、初診日問題については国も救済措置を講じていることがよくわかります。
初診日問題の改善に向けて評価できる取扱いだと思っています。
もちろんすべての初診日問題が解決するわけではありません。
また、これまでに初診日問題で障害年金をあきらめてしまったひとたちの中には、こういった取扱いがなされていることを知らないでいるひとがいるもの事実です。
再度の障害年金申請で支給決定が見込まれる場合もありえますので、こういった取扱いの周知徹底が望まれるところです。
さいごに
今回は障害年金の申請の初診日問題について解説してきました。
筆者の基本的スタンスは「障害年金は自分で申請できる」というものです(社会保険労務士がそんなことをいうのも少しへんかもしれませんが)。
そのようなひとに向けた記事も書いていますので、こちらにご紹介しておきます。
あわせて読んでいただければと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
<スポンサードリンク>

ボードゲーム系社労士&FP
とっくんセンセ
(徳本 博方)
ボードゲーム系社労士&FP
50代おひとりさま予備軍
「ゆとり・つながり・まもり」の3つの「り」メイクでおひとりさまのシングルライフステージをサポート
ボードゲームで楽しく「つながり」をつくり、キャリア相談・資産形成相談と年金サポートで「ゆとり」を、成年後見で最終的な「まもり」をお届けします
- 資格
- 社会保険労務士
- ファイナンシャルプランナー(2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFP)
- 宅建士
- 経歴
- 一般社団法人萩長門成年後見センター事務局長(現)
- 弁護士事務所パラリーガル(勤務17年以上)
- 山口県萩市出身
- 萩高校、慶応義塾大学文学部