ディプロマシールール説明 基本編(1) ~概要・勝利条件
2020.02.05
もくじ
初心者向けディプロマシー基本ルール(1)
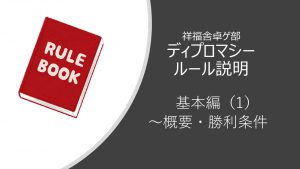
オフィス北浦が主宰する祥福舎卓ゲ部では、対面型のディプロマシーというボードゲームを行っています。
参加者は初心者さんが多いので、その都度ルール説明の時間を1時間程度設けていますが、事前に基本的なことを確認できるように、こちらのサイトでも説明していきたいと思います。
第1回目は、ゲームの概要と勝利条件について、ご説明します。
ディプロマシーってどんなゲームなの?
ディプロマシーは、各プレーヤーが第一次世界大戦前のヨーロッパの7ヶ国(イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オーストリア=ハンガリー、ロシア、オスマン=トルコ。一部アジア地域の国もありますが)に分かれて、補給都市と呼ばれるマップ上のエリアを自国の軍隊によって占有していくゲームです。
各プレーヤーは自分の担当する国の外交官となり、各国と外交(交渉)をして、自国の軍隊の行動を決定していきます。
サイコロを振ったり、(イベント)カードを引いたりといったことはなく、交渉のみでゲームを進めていきます。
そのため、このゲームは運の要素がほとんどなく(強いて言うなら、運が関係するのはどの国を誰が担当するかを決めるあたりでしょうか)、各プレーヤーの交渉力と戦略性がとても重要になるゲームだといえます。

このゲームの特徴は、各国の軍隊の力が均衡しているというのがあります。
各軍隊ユニットの力は例外なく同等ですし、初期配置の各国の軍事力(補給都市及び軍隊ユニットの数)はほぼ均衡しています(初期配置ではロシアだけが他国にくらべて1つだけ補給都市及び軍隊ユニットが多いです)。
これが何を意味するかというと、各国は単独ではまず勝てないということです。
つまり、勝つためにはどうしても他国の協力が必要になるのです。
また、もうひとつのこのゲームの特徴としては、外交(交渉)による合意には、ルール上の何らの拘束力がないというのがあります。
つまり、裏切ってもペナルティーはないということです。
いえ、むしろ裏切らなければ勝てないゲームなのです。
協力しなければ勝てない。
裏切らなければ勝てない。
この矛盾する二つの原理の間で、7人のプレーヤーは悩み、決断することになります。
このような各プレーヤーの思惑が錯綜し、思わぬ展開となっていくのがこのゲームの醍醐味といえるでしょう。
このゲームでプレーヤーは、各国と交渉する「外交官」としての側面と、軍事行動を決定する「司令官」としての側面を併せ持っています。
しかし、その本質はゲーム名「ディプロマシー」(外交)が表すとおり、「外交官」としての側面にあります(ルールブックには「司令官であるより外交官であれ」といった内容がかかれていますし)。
思う存分、外交官としての交渉力を試してください!
現場はどんな雰囲気なの?
祥福舎卓ゲ部で行うディプロマシー会の現場の雰囲気は、おおむね和気あいあいとバトルをしています。
毎回はじめましての方も多いので、各プレーヤーさんが節度をもってゲームをされているのだと思います。
下の画像は、ドイツ、オーストリア=ハンガリー、オスマントルコの3ヶ国がゲームボードを囲んで作戦を協議しているところです(この横で、イギリスとロシアが協議をしていましたし、フランスとイタリアは廊下に出て秘密会議を行っていました)。

ただ、このゲームはシステム上裏切り行為が必須となりますので、ぎすぎすした雰囲気になることも当然想定しておくべきでしょう。
そこで、祥福舎卓ゲ部で行うディプロマシー会では、次のようなお約束をしてもらっています。
- ノンアルコール・ノンスモーキングです
一度、バーを貸し切りにして「ほろ酔いディプロマシー」という企画をしたのですが、なかなかのカオスとなりました(それはそれで盛り上がったのですけどね)。
アルコールが入ると、判断力や注意力も落ちるので、命令書のミスも頻発したように思います。
アルコールがない方がゲームがスムーズに進むのは確かでしょう。
あと、非喫煙者さんのためにノンスモーキングとしています(適宜休憩時間を挟みますので、その際に所定の喫煙スペースで喫煙してもらいます)。
- 個人名で呼ばずに、国名で呼び合いましょう
祥福舎卓ゲ部で行うディプロマシー会では、プレーヤーさんに各国旗のネームプレートを付けてもらい、お互いを「イギリスさん」とか「フランスさん」といったように国名で呼び合うようにしてもらっています。
オーストリア=ハンガリーは長いので「オーストリアさん」とか「オーハンさん」と言ったりします。
これらは、あくまでプレーヤーさんが各国をロールプレイしているということを認識するためです。
こうすることで少しでもゲームでのヘイトをリアルに持ち越さないようにできるのではないかと思っています。
- 外交フェイズ以外ではゲームに関することは会話しないでください
このゲームでは、同盟国が命令書の記載ミスをしたとか、合理的でない行動をとったとか、自分の思い通りにならないことが多発します。
これは7人ものプレーヤーがそれぞれの思惑で動くので、しかたのないことです。
そんなときにはつい「なんでそんなことを」と相手を責めてしまいたくなります。
ただ、それを口に出してはいけません。
誰にでもミスはありますし、もしかしたらミスにみせかけた戦術的な行動かもしれないのです。
そこで、外交フェイズと呼ばれる各国の交渉時間以外は、ゲームの内容に関することは会話しないということを徹底してもらっています(雑談はオッケーです)。
これらを行っても、ときには雰囲気が悪くなることがないわけではありません(負けがこんでくると投げやりな態度になるとか、調子に乗ってヘイトを集めすぎて孤立してしまうとか)。
そんなときには、それも含めてディプロマシーだと割り切るようにしています。
ただゲームマスターとしては、プレーヤーの皆さんに快適な雰囲気の中で遊んでもらえるように、できるだけの配慮をしていこうと思っています。
<スポンサードリンク>
どうなったら勝ちなの?
ディプロマシーの勝利条件としては、
- 1ヶ国が18の補給都市を占有すること
が原則です。
補給都市は全部で34ありますから、その過半数を占有するということです(半数が17ですので、過半数は18になります)。
この他にも、停戦合意というのもあります。
もっとも、18の補給都市を占有するには、かなりの長時間を要します。
そこで、ハウスルールを設けることも多く、その場合には、
- 1ヶ国が**の補給都市を占有すること(**は18以下)
- 19**年*ターン終了時にもっとも多い補給都市を占有していること
のどちらかを充たすこととすることがあります(19**年とか*ターンというのはゲーム進行の時間的な単位です)。
祥福舎卓ゲ部で行うディプロマシー会では、
- 1ヶ国が12の補給都市を占有すること
- 1905年秋ターン終了時にもっとも多い補給都市を占有していること(ただし、GMの判断により、終了ターンを前後させることがあるが、遅くとも1ターン前には事前に告知する)
のどちらかを充たすこととすることが多いです。
いずれにしても、ゲーム開始時に勝利条件は明示させていただきます。
また、各プレーヤーには敗北条件もあります。
それは、保有する軍隊ユニットがすべてゲームボード上からなくなること(かつ増設可能性もなくなること)です。
「滅亡」といったりします。
滅亡した国のプレーヤーはその後ゲームに参加することはできません。
祥福舎卓ゲ部では、GMのサポートをしてもらうようにしていますので、ご協力をお願いいたします。
さいごに
いかがでしょうか。
ディプロマシーの雰囲気がいくらかでも伝わったでしょうか。
友情破壊ゲームだとかサークル崩壊ゲームだとか、なにかと揶揄されることもあるディプロマシーですが、交渉力や決断力を鍛えることのできる楽しいゲームだと思っています。
また、ヨーロッパ各国の地政学上のパワーバランスを「自分ごと」として捉えることのできる知的なゲームでもあります。
だれだってみんな最初は初心者です。
興味のある人はぜひ挑戦してみてください!
次回からは、基本的なルールについてお話できればと思っています。
ディプロマシーの購入ご検討の方は下記のAmazonのリンクをご参照ください(スポンサードリンク)。
あわせて読んでいただきたい記事
ディプロマシールール説明 基本編(4) ~ユニットの初期配置
ディプロマシールール説明 基本編(6) ~命令記入フェイズ 維持命令
ディプロマシールール説明 基本編(7) ~命令記入フェイズ 移動命令
ディプロマシールール説明 基本編(8) ~命令記入フェイズ 支援命令
ディプロマシールール説明 基本編(9) ~命令記入フェイズ 輸送命令
