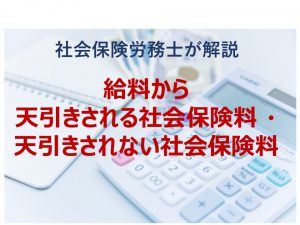新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減って国民年金保険料を支払えない人のために免除の臨時特例を社会保険労務士が解説
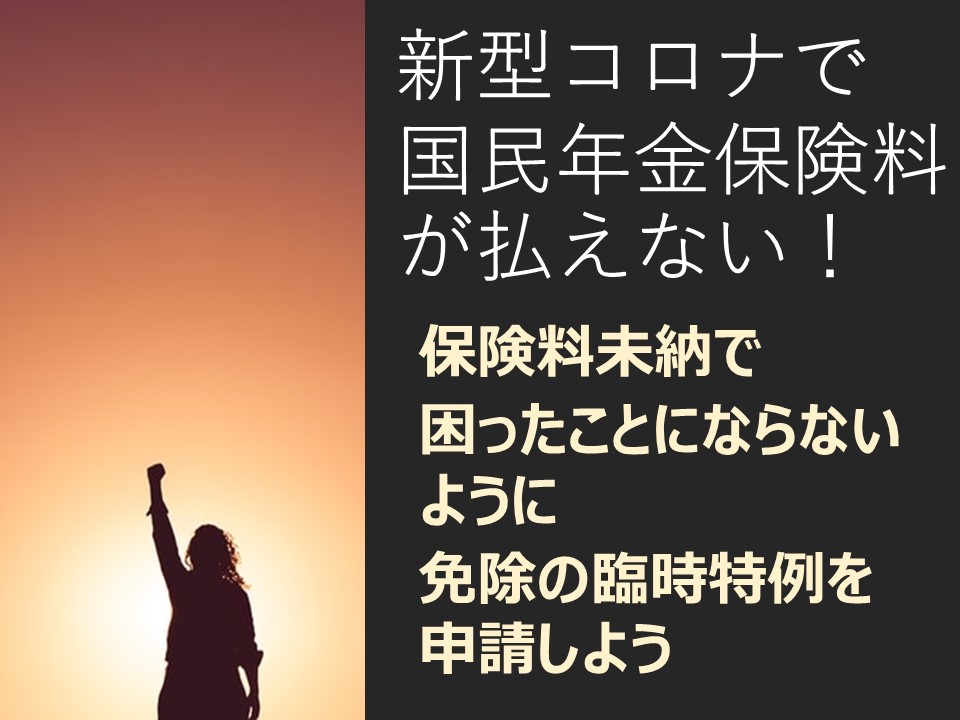
社会保険労務士・オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
今回は、公的年金の国家資格である社会保険労務士が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で収入が減少した場合の国民年金保険料免除の臨時特例についてお話します。
新型コロナウイルス感染症の影響で
- 失職して厚生年金の被保険者から国民年金の第1号被保険者になった人
- アルバイト先が休業して収入が少なくなった人
- 取引先からの受注が減少したフリーランスの人
こういった人たちにはぜひお読みいただきたい記事です。
2020年4月~2021年3月分の国民年金保険料は月額1万6540円です。
収入が減った人にとってはつらい支出だと思います。
どうにかならないものでしょうか。
この点について、この記事でお伝えしたいことは、
- 臨時特例を申請して当面の国民年金保険料の支払を回避しよう
- 未納は絶対に避けよう
- 将来の国民年金(老齢基礎年金)を満額もらうための方法も知っておこう
の3点です。
順を追ってお話ししていきます。
なお、この記事は投稿日(2020年5月6日)現在の情報を元に執筆されています。
<スポンサーリンク>
臨時特例を申請して当面の国民年金保険料の支払を回避しよう
2020年5月1日から国民年金保険料免除の「臨時特例」の申請手続が可能になりました。
この臨時特例によって、対象者は2020年2月~6月分の国民年金保険料(全額または一部)が免除されます。
仮に2~6月までの5ヶ月間の国民年金保険料が全額免除された場合には、8万2700円の支払を免れることができます。
当面の家計に与えるインパクトは大きいと思います。
経済的に困っている人は積極的に申請したいところです。
どんな人が対象?
臨時特例の対象者は、
- 2020年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
の2点をいずれもみたした人です。
学生の場合には、別に「学生納付特例の臨時特例」の対象になります。
具体的にはいくら減ったら対象になる?
臨時特例の対象となるには
- 当年中の所得の見込みが
- 現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になる
と見込まれることが必要です。
この2点について具体的に説明します。
まず、「当年中の所得の見込み」の計算方法です。
- ステップ①:2020年2月以降で収入が減少した月を任意で選ぶ(一番減った月を選べばよいでしょう)
たとえば、アルバイトのAさん(未婚の一人暮らし)が去年の3月は15万円の収入があったのに、今年の3月は7万円になったような場合を想定してみましょう。
- ステップ②:①で出した金額を12倍して1年分の「収入見込額」をだす
Aさんの場合には、7万円×12=84万円が1年分の「収入見込額」です。
- ステップ③:控除相当額をだす
Aさんのような給与所得者の場合には、給与所得控除をだします。
給与所得控除は、②の1年分の「収入見込額」×40%で計算しますが、この額が65万円未満の場合には一律65万円です。
Aさんの場合、84万円×40%=33万6000円ですので、65万円が給与所得控除になります。
- ステップ④:②の1年分の「収入見込額」から③の控除相当額を引いて「所得の見込額」をだす
Aさんの場合、84万円-65万円=19万円が「所得の見込額」です。
次に、「現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準」を確認しておきます。
それぞれの免除区分については、
- 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 以下
- 4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
- 半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
- 4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
とされています。
つまり、先ほど計算した「所得の見込額」がこの区分のどこに該当するかで、いくら免除されるのかが決まるということです。
Aさんの場合には、「所得の見込額」19万円が、全額免除の基準(57万円)以下ですので、全額免除の基準を満たしています。
ここで注意が必要なのですが、「所得の見込額」は本人だけではなく、配偶者(夫や妻のこと。内縁関係も含みます)及び世帯主の「所得の見込額」もチェックされるという点です。
Aさんの場合には、未婚で独り暮らし(配偶者や他に世帯主がいない)だったので、Aさんだけを計算すればよかったのですが、本人のほかに配偶者や世帯主がいる場合にはそれだけでは足りません。
配偶者や世帯主の全員について「所得の見込額」を計算して、全員が免除区分に該当する必要があるのです。
ただし、配偶者や世帯主の「所得の見込額」の計算は必ずしも本人と同じ月を用いて計算する必要はありません(一番収入が減った月を選んでいいということです)。
いつからいつまでいくら免除される?
現在のところ、臨時特例は2020年2~6月までの5ヶ月分の国民年金保険料が免除の対象です。
どの月の収入を元にしても、2月まで遡って適用可能です。
ただし、先に納付された保険料は還付されません。
なお、前納制度(半年分、1年分、2年分等のまとめ払いのこと)を利用している人の場合には免除申請を行った月以降の保険料相当額は還付可能です。
免除後に支払わなければならない具体的な1ヶ月分の保険料は、
2020年2~3月分
- 全額免除:0円
- 4分の3免除:4100円
- 半額免除:8210円
- 4分の1免除:1万2310円
2020年4~6月分
- 全額免除:0円
- 4分の3免除:4140円
- 半額免除:8270円
- 4分の1免除:1万2410円
です。
全額免除以外の免除の場合、この金額を納付しなければ、その月は「未納」扱いとなるので注意が必要です。
将来の年金はどうなる?
臨時特例が将来もらえる老齢基礎年金(原則65歳になったときからもらえる国民年金)の額に与える影響について確認しておきましょう。
老齢基礎年金の額は、年額で78万0900円に改定率をかけた額とされています。
改定額は毎年変わります。
ちなみに、2020年度の老齢基礎年金の額は、年額で78万1700円(満額)です。
これは40年間(480ヶ月)全額を納めた場合の額です。
臨時特例での免除のように、保険料を全部または一部しか納めていない人の場合には、その期間減額されることになります。
具体的な減額率は、
- 全額免除:2分の1
- 4分の3免除:8分の3
- 半額免除:4分の1
- 4分の1免除:8分の1
です。
ここはなかなかピンとこないところですが、ざっくりとイメージしてもらうために、臨時特例で5ヶ月間免除を受けて、そのほかの期間は満額納付したとして、改定率をかける前の額(78万0900円)で比べてみましょう。
- 全額免除:(78万0900円×475/480)+(78万0900円×5/480×1/2)=77万6833円(4067円減額)
- 4分の3免除:(78万0900円×475/480)+(78万0900円×5/480×5/8)=77万7850円(3050円減額)
- 半額免除:(78万0900円×475/480)+(78万0900円×5/480×3/4)=77万8866円(2034円減額)
- 4分の1免除:(78万0900円×475/480)+(78万0900円×5/480×7/8)=77万9883円(1017円減額)
ぱっとみるとそこまで減っていないような感じもしますが、老齢基礎年金は終身年金(死ぬまでもらえる年金)ですので、これが10年、20年と積み重なると差額は大きくなっていきます。
<スポンサーリンク>
未納は絶対に避けよう
臨時特例の申請もせずに、国民年金保険料を払わずにいるとどうなるのでしょうか。
これを国民年金保険料の未納といいます。
国民年金保険料の未納を避けるべき理由を簡単にあげておきます。
将来の年金が減額されるだけでなく、まったくもらえなくなる可能性があります
未納期間の将来の年金額は0円です。
これに対して、先ほど計算したように、臨時特例の全額免除の場合には1/2が減額されるだけですみます。
同じ保険料をまったく払わない状態なのに、大きく変わってきます。
しかし、ペナルティーはこれだけではありません。
保険料の未納を続けていくと、年金がまったくもらえなくなる可能性があるのです。
具体的には、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として10年以上必要です。
もしも資格期間が10年未満であった場合には、将来の年金は0円(無年金)になってしまいます。
障害年金がもらえなくなる可能性があります
障害年金をもらうためには「保険料納付要件」をみたす必要があります。
具体的には、初診日の前日において、
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(「2/3要件」)
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(「1年要件」)
のどちらかをみたす必要があります。
「2/3要件」であっても「1年要件」であっても、未納期間は不利に扱われます。
もしもこれらの保険料納付要件がみたせなければ、その時点で障害年金はもらえません。
延滞金が発生したり、強制徴収による差押えの可能性があります
国民年金保険料の未納に対しては、延滞金が発生することがあります。
具体的な延滞金割合(2020年1月1日から12月31日)は、
- 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで:2.6%
- 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降:8.9%
です。
また、一定の所得が認められるようなケースなどでは、強制徴収(差押え)の可能性もあります。
つまり、未納が続くと銀行口座や不動産などを差押えられる可能性があるということです。
なお、あまり知られてはいませんが、国民年金保険料は本人に納付義務があるだけでなく、配偶者や世帯主にも連帯納付義務があります。
そういった連帯納付義務者に迷惑をかけてしまうこともありえるのです。
このような理由から、国民年金保険料の未納はできるだけ回避したいところです。
今回の臨時特例を積極的に利用して、未納のまま放置することは避けましょう。
<スポンサーリンク>
将来の国民年金(老齢基礎年金)を満額もらうための方法も知っておこう
臨時特例で国民年金保険料が免除された場合には、「未納」による不利益は受けませんが、将来の年金が減らされてしまうことは避けられません。
そこで、臨時特例で免除された人が将来の年金を満額もらうためにできることをお伝えしておこうと思います。
追納制度
臨時特例で免除された国民年金保険料は、「追納」することができます。
追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間についてです。
ただし、免除を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
2年度以内であれば加算されませんので、早めの追納がお得です。
追納後は、保険料が全額納付されたものとして将来の年金額が計算されます。
任意加入制度
追納期間を経過して追納ができなくなった場合には、60歳になったあとに国民年金の任意加入制度を検討してみましょう。
任意加入制度は、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人などのために、60歳以降でも国民年金に加入できる制度です。
任意加入をするためには、
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満であること
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと
こういった要件をすべてみたす必要があります。
追納できなかったときの手段として覚えておいてください。
厚生年金の経過的加算
国民年金ではないのですが、厚生年金にも老齢基礎年金に相当する給付があります。
それを「経過的加算」といいます。
たとえば、60歳以降に厚生年金の被保険者であった場合(原則70歳に達するまで)、その厚生年金の被保険者期間に応じて、老齢基礎年金に相当する給付が経過的加算として上乗せされます。
上限や計算方法などの詳細は省略しますが、経過的加算は実質的には満額にみたない老齢基礎年金を補充してくれる役割を果たしています。
60歳を超えて厚生年金の被保険者として働くというのも、一つの方法として覚えておいて損はないでしょう。
<スポンサーリンク>
さいごに
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合の国民年金保険料免除の臨時特例についてお話ししてきました。
具体的な手続などは日本年金機構のホームページをご参照ください。
とにかく使える制度はすべて使って、どうにかこの困難な状況を乗り越えていきたいところです。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
前後の記事
前の記事:給料から天引きされる社会保険料・天引きされない社会保険料
後の記事:障害年金はいくらもらえる? 障害年金の金額をざっくり紹介
<スポンサーリンク>
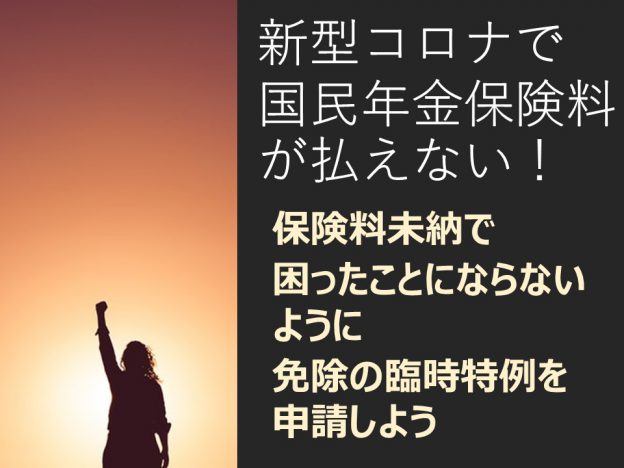



 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。