障害年金の受給が公的医療保険(健康保険等)に与える影響を社会保険労務士が解説
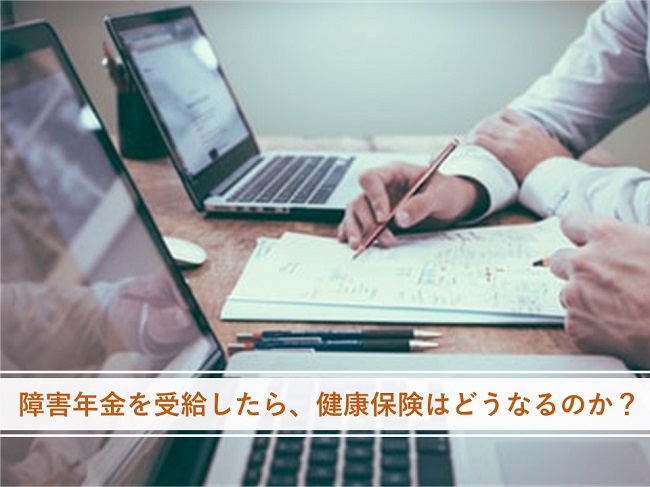
社会保険労務士・オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
今回は、社会保険の国家資格である社会保険労務士が、障害年金を受給した場合に公的医療保険(健康保険等)にどのような影響があるのかを解説していきます。
話を整理するために、
- 会社の健康保険に加入している人
- 家族の会社の健康保険の扶養に入っている人
- 国民健康保険に加入している人
この3つのケースについて考えます。
なお、この記事は投稿日(2020.5.18)現在の情報に基づいて執筆されています。
<スポンサーリンク>
結論から先にいいますと、
- 健康保険の被保険者本人が障害年金を受給しても特に影響はありません
- 健康保険の被扶養者が障害年金を受給した場合には扶養から外れてしまう可能性があります
- 国民健康保険の被保険者が障害年金を受給した場合には保険料が安くなる可能性があります
というお話です。
それでは順にみていきましょう。
<スポンサーリンク>
健康保険の被保険者本人が障害年金を受給しても特に影響はありません
障害年金の受給者が、会社の健康保険に加入している(健康保険の被保険者本人である)場合には、健康保険に与える影響は特にありません。
保険料も変化しませんし、受けられるサービスが変わるわけでもありません。
そのまま健康保険に加入しつづけることができます。
なお、健康状態の問題で会社を辞めるのであれば、一般の退職の場合と同じく被保険者の資格は喪失します。
退職して資格喪失したあとは、①現在の健康保険の任意継続被保険者となる、②家族の健康保険の扶養に入る、③新しく国民健康保険に加入するといったパターンが考えられます。
健康保険の被扶養者が障害年金を受給した場合には扶養から外れてしまう可能性があります
障害年金の受給者が、家族が勤める会社の健康保険の扶養に入ってる(健康保険の被扶養者である)場合には、収入要件に影響があります。
健康保険の被扶養者になるためには、
被扶養者の年間収入が、
- 130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満)
であり、かつ
- 被扶養者の収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること(同居の場合)
- 被扶養者の収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満(別居の場合)
のどちらかであることが原則として必要です。
そして、この「被扶養者の年間収入」には非課税所得である障害年金も含まれます。
つまり、被扶養者の障害年金を含めた年間収入が、
- 180万円以上になった場合
- 180万円未満でも、被保険者の収入の半分以上となった場合(同居の場合)か仕送り額以上になった場合(別居の場合)
には、原則として被扶養者になれない(=扶養から外れる)ということです。
例外として、同居の場合には扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときには、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上となった場合でも扶養が認められることもあります。
障害年金の受給者が扶養から外れた場合には、新たな公的医療保険(ほとんどが国民健康保険になるでしょう)に加入する必要があります。
国民健康保険の被保険者が障害年金を受給した場合には保険料が安くなる可能性があります
障害年金の受給者が、自ら国民健康保険に加入している場合には、国民健康保険を継続できるのはもちろんですが、翌年度からの国民健康保険料が安くなることもあります。
障害年金は非課税所得ですので、障害年金しか収入がない場合にはその人の国民健康保険料の所得割は0になります。
また、国民健康保険料の均等割も低所得であれば一定の減額を受けることができます(この減額を受けるためには、所得がないことを申告する必要があります。詳しくは、「障害年金をもらいはじめたら確定申告をしなければならないの?【年金の常識15】」をお読みください)。
なお、国民健康保険料は世帯主に納付義務が生じます。
なので、たとえば、世帯主である夫は会社の健康保険に加入しているような場合でも、妻が障害年金を受給し始めて扶養から外れて国民健康保険に加入したような場合には、妻の国民健康保険料を世帯主である夫が納付する義務が生じます。
<スポンサーリンク>
まとめ
今回は、障害年金を受給した場合に公的医療保険(健康保険等)にどのような影響があるのかという問題について、
- 健康保険の被保険者本人が障害年金を受給しても特に影響はありません
- 健康保険の被扶養者が障害年金を受給した場合には扶養から外れてしまう可能性があります
- 国民健康保険の被保険者が障害年金を受給した場合には保険料が安くなる可能性があります
というお話をしてきました。
日本では国民皆保険制度が整っていますので、何らかの公的医療保険に加入するのが原則です。
公的医療保険にも複数の種類がありますのでややこしいところではありますが、いろいろと情報を集めて対応してもらえればと思います。
なお、公的医療保険には原則75歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険制度というものもありますが、国民健康保険の場合とほとんど同じだと思ってください(納付義務者は被保険者本人ですが、世帯主や被保険者本人の配偶者が連帯納付義務者となるといった違いはあります)。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
<スポンサーリンク>

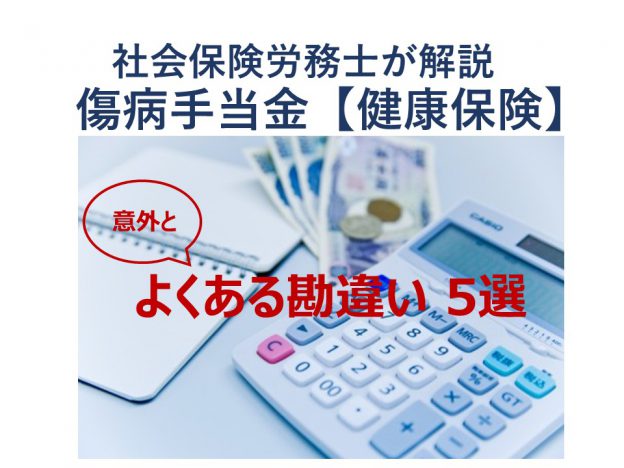

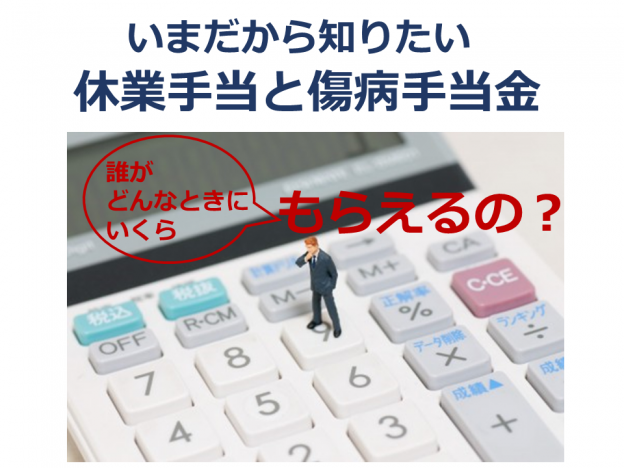
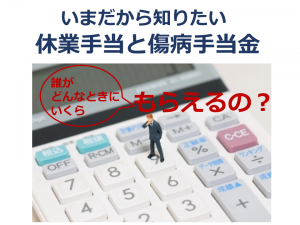 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。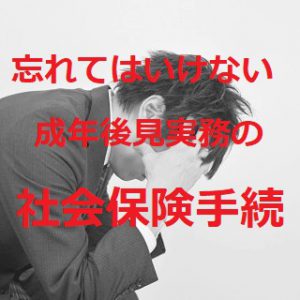
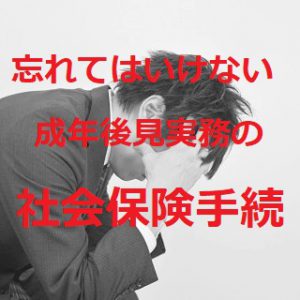 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。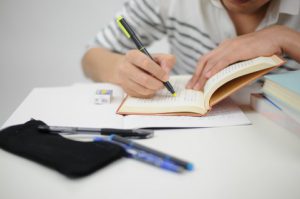 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。