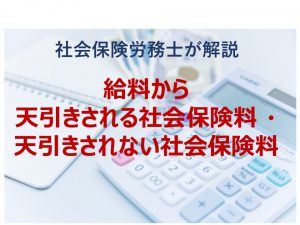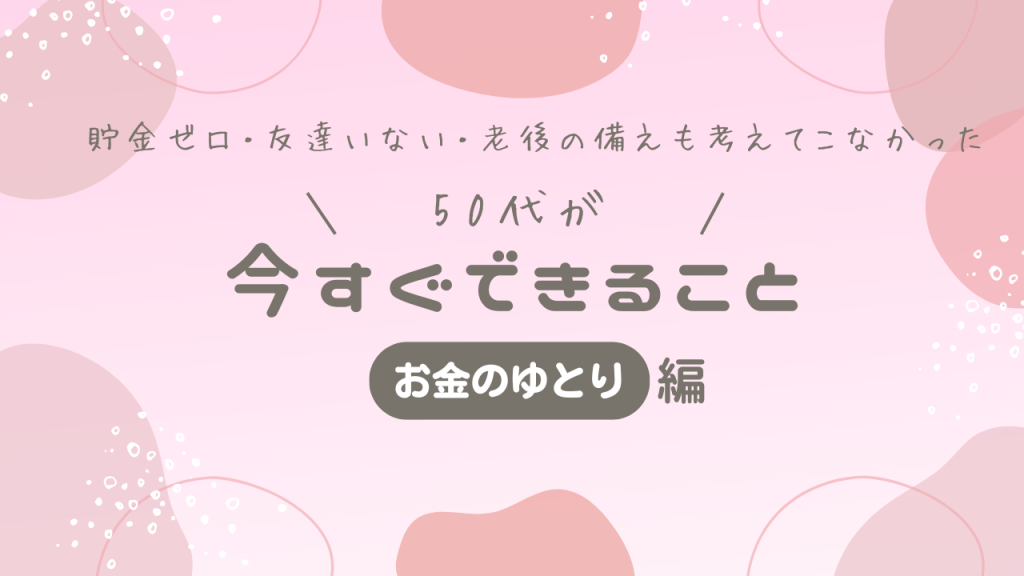
今回は、50代おひとりさまの筆者が、貯金ゼロ・友達いない・老後の備えも考えてこなかったという同世代の人に向けて、今すぐできることを「ゆとり」「つながり」「まもり」の3つの「り」メイクにそって3回に分けてご紹介していきます。
筆者は50代未婚のボードゲーム系社労士&ファイナンシャルプランナーで、現在は「5080」問題の当事者として両親と同居しつつ「こどおじ」生活をしています。
第1回目は貯金ゼロからの「お金のゆとり」編です。
結論から、言います。
「今ならまだ大丈夫です!」
ここでは、ことさらに不安をあおったり、できもしない高い目標を無理強いしたりもしません。
ポイントは、「引き算」。
それでは、「お金のゆとり」編、スタートしましょう。
お金の不安:「貯金がなくても大丈夫?50代から始める“後悔しない”お金のゆとりの考え方」【引き算思考】
◆ よくあるお悩み
- 「このまま一人で老後を迎えるのが不安」
- 「貯金がゼロ。年金だけで暮らせるの?」
- 「節約しろと言われても、何をどうすれば…」
こんなお悩みを持っている50代の方に向けての「ゆとり」の「り」メイクです。
解決のヒントは、“足し算”ではなく“引き算”思考。
50代からの「お金のゆとり」は、派手に稼ぐことではなく、無駄なものを引き算して、身の丈に合った暮らしに整えることが重要になってきます。
🔹1. まずは生活を見直す:「引き算」節約術のすすめ
スタートはモノの引き算
引き算の基本は、モノを捨てることです。
モノを捨てることの強味は、誰にだってできることです。
時間と労力は必要ですが、自分でモノを捨てるにはほとんどお金はかかりません(最低限の処分費用は必要ですけど)。
モノを捨てる作業を始めると、持っているモノの棚卸ができて、何がどこにあるのか把握できるようになります。
思わぬ掘り出し物が見つかることも。
そして、だんだんとスペースに余白が生まれると、本当に不思議なんですけど、気持ちにも余裕が生まれてくるんです。
これは、「放活(はなかつ)」を始めた筆者がリアルに今体験していることです。
売れるものは売ってしまえば、資産化もできます(ただ、モノを売る作業にどれだけの時間と労力を割けるかは人によります。割に合わないと考えるなら、迷わず廃棄処分した方がいい場合もあります)。
コンビニ・外食の引き算=最強の資産形成
次に、コンビニと外食を引き算していきましょう。
もちろん、ゼロにすることは無理でしょう。
でも、ぼちぼち50代おひとりさまの嗜みとして、簡単な自炊にチャレンジしてみませんか。
最初はサラダ作るだけでもいいんです。
というのも、50代がお金をかけずにできる最大の自己投資は「自炊による健康づくり」だと思っています。
コンビニと外食の引き算で、生活習慣病のリスク低減効果も期待できます。
ついでに、ぜい肉貯金も引き算できればもうけものです。
食費の節約効果はもちろん、“長く働ける身体”を作るという最強の資産形成にもなります。
とにかく、おひとりさまの最後の資本は「身体」ですから。
ちなみに、筆者の最初の自炊?チャレンジは、「めんつゆ」づくりでした(これを自炊と言ったら、ガチ勢からボコボコにされそうですけど)。
意外に美味しかったし、何より自分で作れるんだとちょっと感動したものです。
サブスクの引き算はマスト
3つめは、固定費を見直すこと。
これは、ファイナンシャルプランナーとしては面白みのない提案なんですけど、この引き算はマストなので外せません。
保険・スマホ・サブスクサービスなどなど、見直せそうなものの一つや二つは誰にだってあります。
この、チリつも引き算は侮れないんですよ。
だって、仮に月に1万円引き算できれば、年間12万円。
65歳まであと10年あるとすれば、これだけで120万円なんですからね。
さらに言えば、賃貸の人は家賃という最大のサブスクがあります。
ここに手を付けるかは、検討のしどころ。
引越しを考えるうえで、1つめの「モノの引き算」がここでも役に立ってきます。
🔹2. 最初の目標は「貯金100万円」
次に、ではいくら貯めればいいのかを考えていきましょう。
これは、上を言えばきりがないです。
なので、貯金ゼロの人は、まずは緊急用資金として100万円の貯金を確保していきたいところです。
月に2万円なら50ヶ月(4年と2ケ月)で100万円ですね。
これに着手できれば、やってるうちに貯金額も増やすことができて、もっと早くに目標達成ができると思います。
だって、引き算生活をやっているだけで、それだけで多分2万円くらいは余剰がでているはずですし、それに引き算生活を続けていけば、自然と本当に必要なモノ以外には「モノを買わなくなる」んです。
何か買おうと思ったときに、これどうやって捨てようって考えると、かなり強力なブレーキがかかります。
とにかくここでのポイントは、老後資金2,000万円問題よりも、できることから「始める」ことです。
100万円たまったら、次のことを考えましょう。
🔹3. 借金があるなら“リセット”を検討
ここからは、ちょっと本音で話します。
借金、大丈夫ですか?
もし、貯金ゼロの原因が借金の返済にあるなら、話は少し変わってきます。
筆者は法律事務所のパラリーガルとして、個人・法人を問わず、これまでに100件以上の債務整理にかかわってきました。
借入の理由は人それぞれでした。
でも、共通していたのは、最終的には自転車操業といって、借金で借金を返すようになっていたことです。
こんなかんじで、もしも消費者金融やカードローンの返済に追われている場合は、まよわずに債務整理(任意整理・個人再生・自己破産など)での生活再建を検討してください。
これは、直ちにです。
この問題は単独ではどうにもなりません。
ひとりで抱え込まず、法テラスや専門家(弁護士・司法書士)に相談を。
筆者は、パラリーガルとして、債務整理の後に、再出発された人たちを目の当たりにしてきました。
本当に債務整理の前と後ではみなさん表情が違うんです。
まずは、マイナスからゼロに戻すことが肝心です。
債務整理は、まさに借金の引き算。
本当の意味で貯金ゼロから再スタートしても、50代ならまだ大丈夫です!
あ、あと「モノの引き算」との関係でいえば、支払いが完済していないモノは捨てたり売ったりしないでくださいね。
債務整理の際に返却が必要になるケースもありますので。
🔹4. 長く働ける環境を準備をしよう
最後の引き算は、働き方です。
50代は、「働き方のリセット」を考えるにも良いタイミング。
最近、「生涯労働=負け組」とか言われることもありますが、筆者は必ずしもそうは思っていません。
もちろん、生活のために身体と心をすり減らしてやりたくない仕事で働くというのは辛いことです。
でも、高齢期に働くことは、「健康維持+人とのつながり+収入確保」の3つを兼ねていて、うまく働くことができればそれは生涯の生きがいにもなります。
経験を積んだ50代の今だからこそ、負担の少ないパートやフリーランス、副業などにも目を向けて、無理なく長期間稼ぐことができる環境を考えるにはちょうどいい時期なのです。
すぐにリタイヤとかを考えるのではなく、今の仕事のリソースを徐々に引き算して、ちょこっと次の20年を考えてみてもいいのではないでしょうか。
社労士の立場から言えば、これから労働人口が減少していくのが確実な以上、高齢者が働きやすく、十全に活躍できる環境を整えるのは、企業の生き残り戦略にもかかわることです。
時代の流れとして、情報収集だけでもやっておいて損はないはずです。
さいごに
人生100年時代と言われて久しいですが、50代で「貯金がない=人生詰み」ではありません。
今ある生活を少しずつ整えて、体を大事にしながら「ゆとり」を育てていけば、50代からでも十分に間に合います。
50代「お金のゆとり」のポイントは引き算思考です。
働いてお金を稼いでも、稼いだ分だけ使ってしまう。
それがうまく回っているうちはいいのですけど、50代になるとそろそろシフトチェンジの時期だと思います。
<スポンサードリンク>

ボードゲーム系社労士&FP
とっくんセンセ
(徳本 博方)
ボードゲーム系社労士&FP
50代おひとりさま予備軍
「ゆとり・つながり・まもり」の3つの「り」メイクでおひとりさまのシングルライフステージをサポート
ボードゲームで楽しく「つながり」をつくり、キャリア相談・資産形成相談と年金サポートで「ゆとり」を、成年後見で最終的な「まもり」をお届けします
- 資格
- 社会保険労務士
- ファイナンシャルプランナー(2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFP)
- 宅建士
- 経歴
- 一般社団法人萩長門成年後見センター事務局長(現)
- 弁護士事務所パラリーガル(勤務17年以上)
- 山口県萩市出身
- 萩高校、慶応義塾大学文学部
<スポンサードリンク>
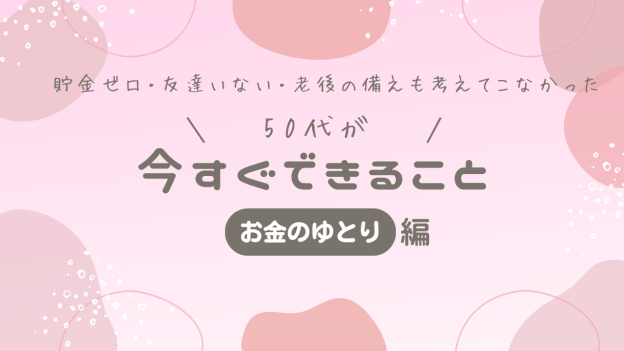






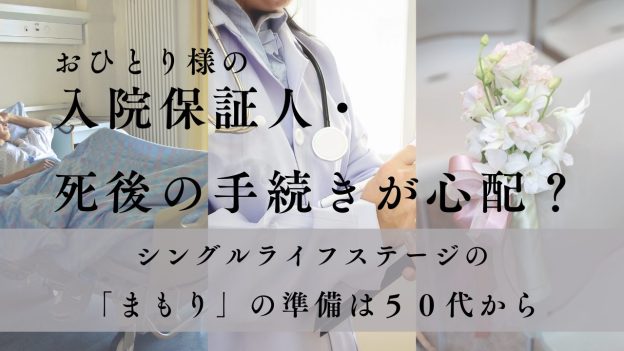
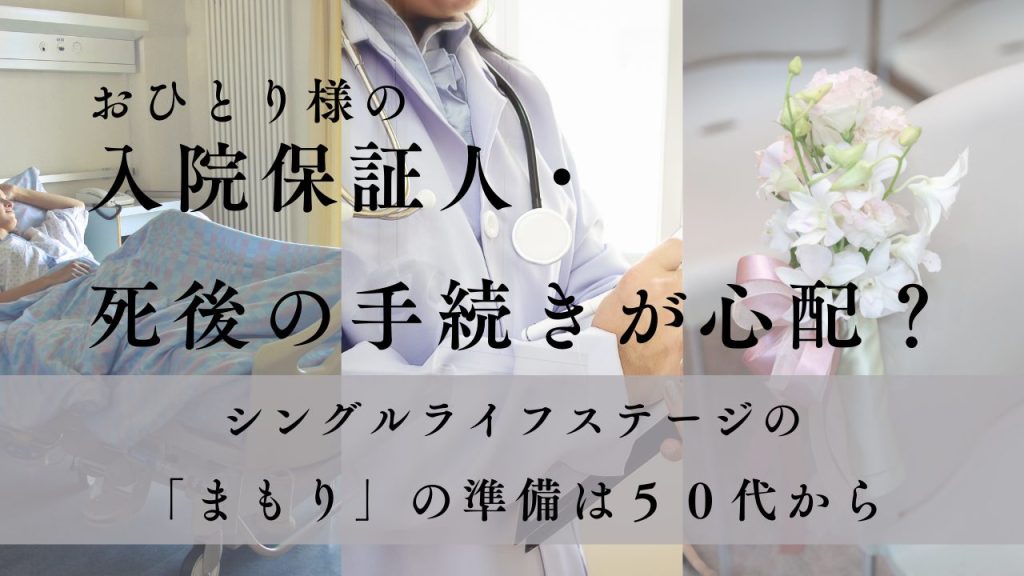




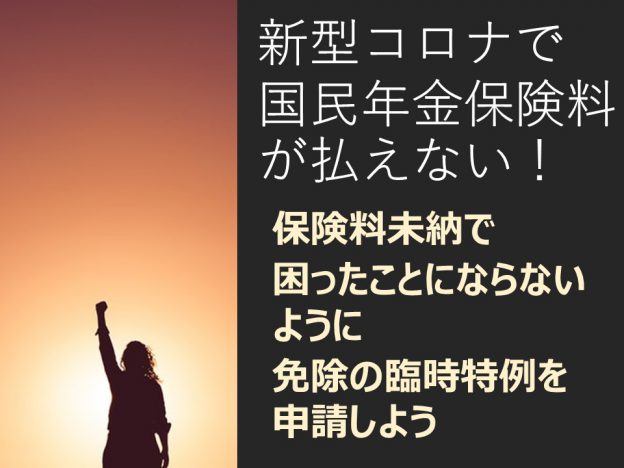
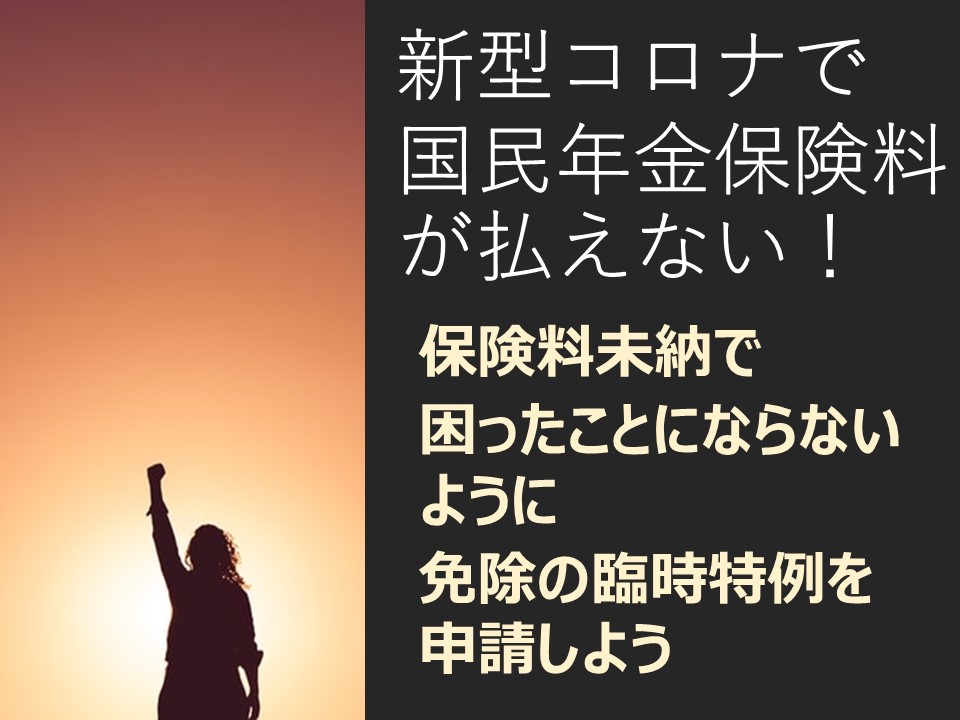
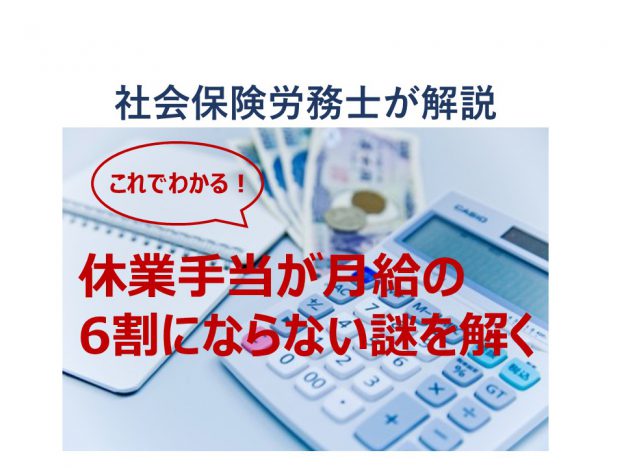
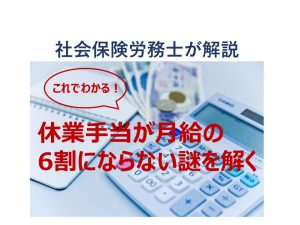 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。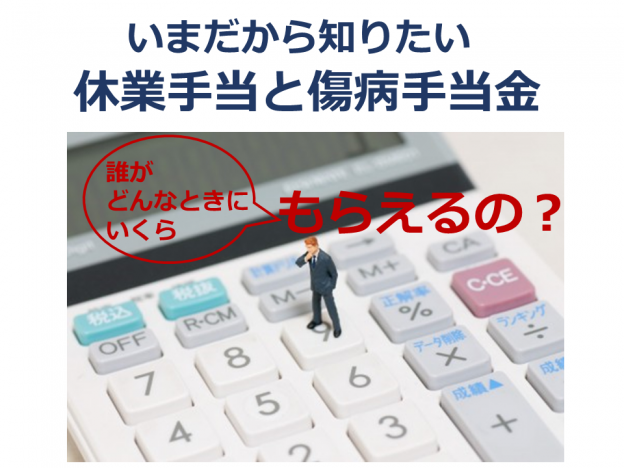
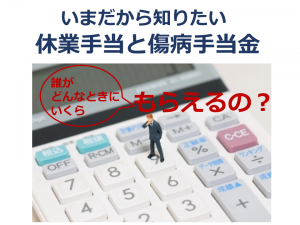 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。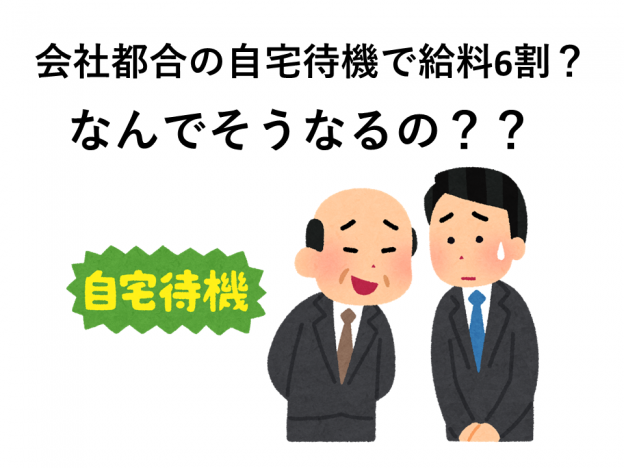
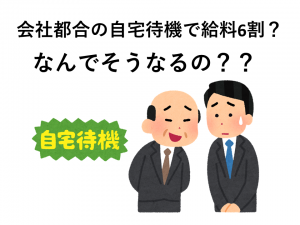 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。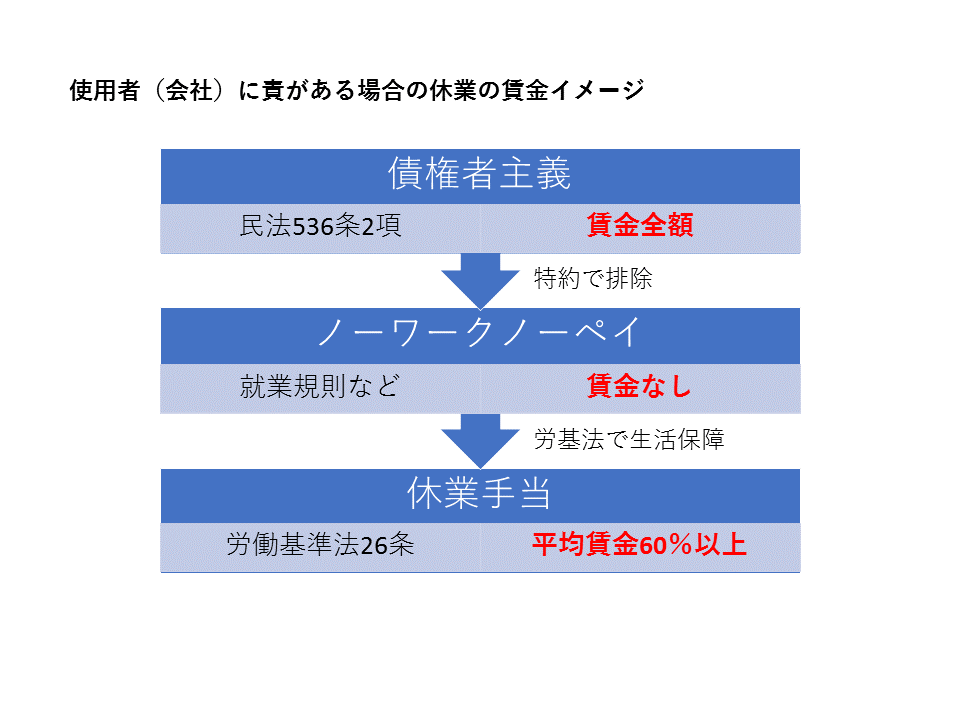

 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。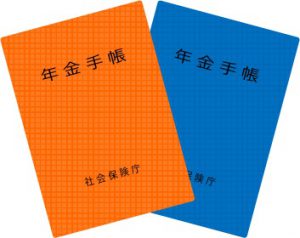 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。 オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトにようこそおいでくださいました。 オフィス北浦のブログサイトへようこそおいでくださいました。
オフィス北浦のブログサイトへようこそおいでくださいました。 人は生きていくうえで、たくさんの意思決定をしています。
人は生きていくうえで、たくさんの意思決定をしています。 今回は、「ボーナス」のお話です。
今回は、「ボーナス」のお話です。 ※7/16追記:本記事には、追加記事があります(
※7/16追記:本記事には、追加記事があります( 新社会人の皆さま、給料から天引きされる厚生年金保険料が、どのように計算されるのかご存じでしょうか。
新社会人の皆さま、給料から天引きされる厚生年金保険料が、どのように計算されるのかご存じでしょうか。 新社会人の皆さん、厚生年金についてどんなイメージを持っていますか。
新社会人の皆さん、厚生年金についてどんなイメージを持っていますか。 皆さん、お金を貯めていますか?
皆さん、お金を貯めていますか? 「お金」の話をしていると、よく財布の話題になります。
「お金」の話をしていると、よく財布の話題になります。